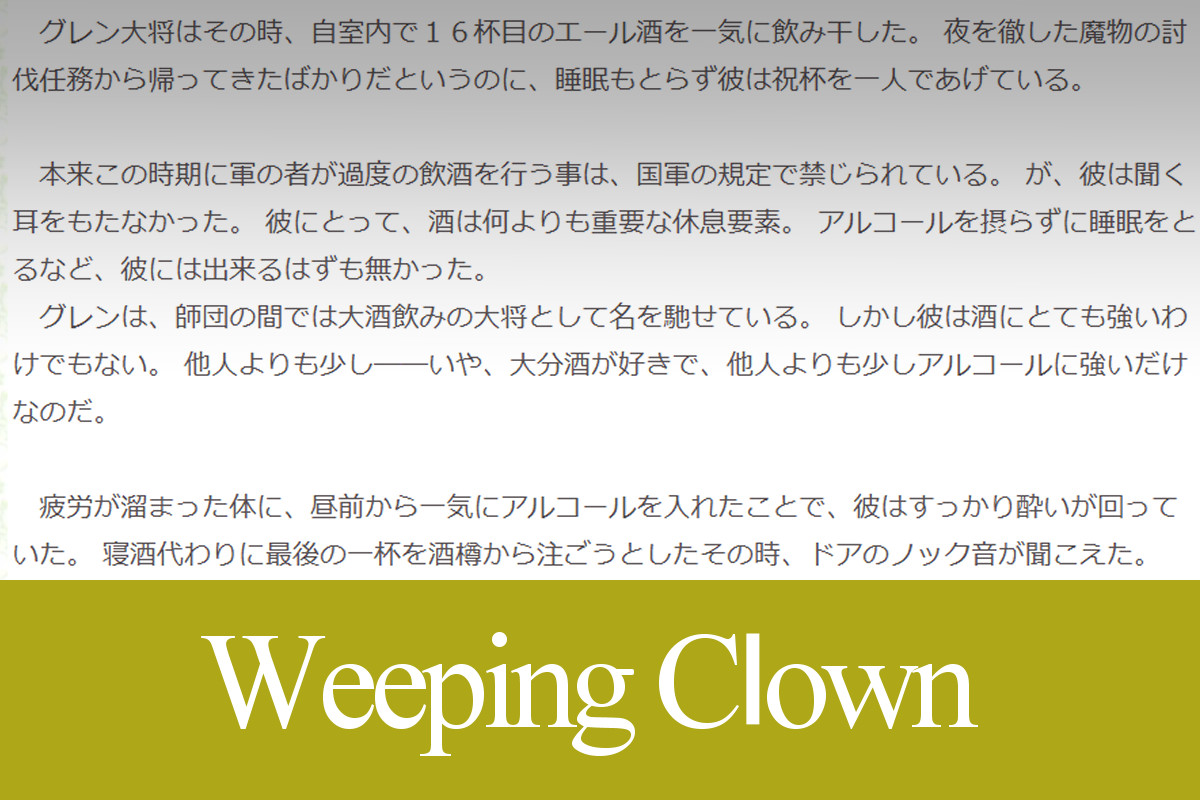プロローグ
グレン大将はその時、自室内で16杯目のエール酒を一気に飲み干した。 夜を徹した魔物の討伐任務から帰ってきたばかりだというのに、睡眠もとらず彼は祝杯を一人であげている。
本来この時期に軍の者が過度の飲酒を行う事は、国軍の規定で禁じられている。 が、彼は聞く耳をもたなかった。 彼にとって、酒は何よりも重要な休息要素。 アルコールを摂らずに睡眠をとるなど、彼には出来るはずも無かった。
グレンは、師団の間では大酒飲みの大将として名を馳せている。 しかし彼は酒にとても強いわけでもない。 他人よりも少し――いや、大分酒が好きで、他人よりも少しアルコールに強いだけなのだ。
疲労が溜まった体に、昼前から一気にアルコールを入れたことで、彼はすっかり酔いが回っていた。 寝酒代わりに最後の一杯を酒樽から注ごうとしたその時、ドアのノック音が聞こえた。
「なんだ」
グレンはドアを開ける。立っていたのは士官だった。弓兵のワルター。階級は確か、ふた月前に伍長に上がったばかりだ。
ワルターは走ってここまで来たようで、軽く息が上がっている。
「突然失礼いたします! グレン大将にどうしても取り次いでほしい、という奴がいまして」
「取り次ぎ? あー、今忙しいから後にしてくれねえか」
正直、対応する気力も集中力もない。それに今は夜中だ。
「それが……」
ワルターの話を聞き終えると、グレンの表情はかわった。手の空ジョッキを乱暴に机へ置き、部下と共に自室を飛び出した。
*
アルファルド王城の北東門、裏。問題の人物はそこにいた。 やってきたグレンの目に最初に留まったのは、小柄な少年。 おそらくアルファルド人ではないのだろう――珍しい色の髪と、大きな瞳が特徴的だ。 少年の手には剣。そして、彼の周囲には、甲胄を着た番兵が数名倒れこんでいた
「おいおい、何だこれは」
グレンは思わず頭を掻いた。ぼさぼさの茶髪が更に乱れる。
「おいチビすけ。これお前がやったのか?」
少年は、グレンの問いかけに少し戸惑ったような、驚いたような表情をみせ、そして言葉を漏らした。
「ほ、本当にきた……」
オレはオバケか何かか、と思いつつ、グレンは少年に言う。
「本当に来た、って、何が?」
「あ、あの」
少年は緊張しているのだろうか、かすかに声を震わせる。
「僕……じゃない、私は、この軍の入隊を志願して来ました。取り合ってくださった方に、 『俺らを倒したら入らせてやるよ』って言われたので、とりあえず、倒してみたんです……けど……」
――いやいや、『とりあえず倒してみた』じゃねえよ。
グレンは自身の目と耳を疑った。少年の周りに倒れているのは、曹長1名、伍長3名、少尉1名。 新兵はいないし、彼ら5人をこの少年1人が倒したなんて、とても信じられない。
少年は絶句するグレンをよそに、続ける。
「それで、そのうち皆さんが話し合いを始めて……『大将呼んでくるからお前は待ってろ!』って言われたので、待ってたんです」
つまり、俺はこの化け物じみた少年のお守りをしろってか。 頭を抱えるグレンの前で、倒れている兵士は悲痛な声をあげる。
「大将、こいつヤバいですよ!10歳のガキだと思ってなめないほうがいいですって!」
「そうですよ大将!俺、コイツに『軍は14歳からだからあと4年待て』って言ったのに頑として聴かなくて、 『じゃあ俺らを倒したら』って言ったらあっさり剣と魔法で倒しやがった!」
「この子普通じゃないですって!」
「ああもう、わかったわかった」
グレンは彼らをとめた。どうやらこの少年は敵ではない。むしろ、進んでこの軍の戦力になりたがっている。
グレンは思案した。
チャンスなんじゃねえか? 自分が戦って、本当に使える人物と思ったなら。年齢や規則なんて、関係ない。 未知数の戦力を持つ少年が、目の前にいる。 使わない手は、ない。
「入隊動機と志望の兵科は?」
「国民を護るため。兵科は……剣を使えるところ」
「魔道師団じゃなくてか?」
少年は深く頷いた。
志望動機と、やる気さえあるならそれでいい。グレンはにやりと笑みを浮かべると、少年へ背を向けた。
「よし! んじゃ、付いてこい。元帥に掛け合ってやるよ」
Ⅰ-1
この王国には、「魔物」が存在する。
それは人間や動物を攻撃し、時に村や町が壊滅するほどの危害を与える。 魔物には生命が無い。外敵からの攻撃を受けないかぎり何十年も何百年も存在しうる。
ゆえに魔物は、国の繁栄を妨げる大きな要因であった。 王国の人口が増加し、町や村の規模が大きくなると、自警団や軍が魔物の討伐隊の編成と派遣を始めた。 結果として大多数の魔物が姿を消した。王国の主要な敵はいつしか、「魔物」から戦争相手の「敵国」に変わった。 しかし今でも、魔物の数がゼロになった事はない。それは同時に、討伐隊の派遣がゼロになることは無いことを意味していた。
そして、4名の男女で編成された討伐隊が今、一体の魔物と対峙していた。
*
人の気配が無い廃村の一角。重苦しい曇天の下で、住居としての役目を終えた家々が並ぶ。 もう何年も前に住民が消えたこの村は、人の代わりに草木が住居を占領した。雑草と低木が鬱蒼と建物を取り囲んでいる。
そんな廃村の片隅で、レイスとリオンは目の前の光景を呆れ半分で見守っていた。
二人の前には、二人の弓兵が互いに向かい合って立っている。鎧で武装した女性兵士、軽装備を纏った若い男性兵士だ。
女性にしてはとても短く切られた茶髪を揺らし、女性兵士は目の前の若い男性弓兵へ怒りの眼差しを向けていた。
「貴様!上官であるこの私に矢を向けるのか!」
叱られている男は、ユーリという。彼は反射的にびくりとのけ反り、つがえたはずの矢を弓から外した。
「ディーナ少将、だからこれは違うんですってば!」
「お前は私の部下失格だ。覚えておけ!貴様の体は、明日にでも矢の的にしてやる!」
「お願いですそれだけは勘弁してください!」
ユーリは震える声をなんとか絞り出し、上官へひたすらに、ただひたすらに詫びる。
弓兵どうしの喧嘩――正確には一方的な叱責だが――を、どう収拾つけるべきか。レイスとリオンは考えていた。 つい先刻まで意気揚々と弓矢を構えていた兵士ユーリが、たかが怒声でこんなにも縮み上がるとは思わなかった。
「ユーリさん……まさかディーナ将軍が一番怖いんですか?」
リオンはユーリにとりあえず話しかけてみた。ユーリはリオンの方へ振り返る。
「ああ怖ぇよ……少将に睨まれると、オレあまりに怖くて動けなくなるんだ。士官時代のトラウマが色々と蘇ってさあ」
「お気持ちはお察しします……。私も昔は散々しごかれましたから」
レイスも同意した。
ディーナ将軍が怒った顔はそんなに怖いのかなぁ、とリオンは思う。 リオンがディーナ将軍と初めて会ったのは、つい数日前のことだ。 人に厳しく、自分にも厳しくあたる印象のある人だったが、そこまで怒鳴り声を張り上げる印象はリオンの中になかった。
しかし、たとえどんなに怖くても今はそれと向き合わなくてはならない。
「ユーリさん、レイス!今はライラさんが戻ってくるまで頑張りましょ!」
リオンはユーリを鼓舞する。そして、言葉をつづけた。
「ここにいるディーナ将軍は、ニセモノ――魔物なんですから!」
*
魔物の中には、変わった攻撃方法をするものがいる。「クラウン」と呼ばれる魔物もそのうちのひとつ。 クラウンは本来小さくて白い球体の姿をしている。 しかし外敵から身を守るために、敵の心を読み、一番「怖い」物そのものに変化し、攻撃をする。 性質や記憶までも、変化する対象と完全に一致する。 まるで役を演じる道化師のようなその性質から、いつしか魔物にはクラウンという名がついた。
ユーリが一番怖いと感じるものは、ディーナ中将。それにクラウンは変化している。 リオン、レイス、ユーリ、ライラの4人がこの魔物を倒すための討伐隊として廃村に派遣された。 しかし、敵の変身能力に踊らされてしまっているのが現状だ。
リオンは杖を両手で握りなおす。ユーリの狼狽っぷりを見るに、ここはレイスとの二人で切り抜けることも覚悟しなければいけない。 討伐隊の残り一人であるライラは、他に敵がいないか隣の居住区まで確認に行っている。いつ頃戻ってくるかは分からない。
リオンの手には、杖がある。その杖は不思議なことに、彼女の思いどおりの形をとることができる。 その杖の力でなんとか、ディーナ将軍の矢を防がなければいけない。 杖の形を変え、盾に……と思った瞬間、ディーナの姿をしたクラウンが矢を番えた。
ディーナ将軍は、昔ロングボウ部隊の隊長だったとレイスから聞いたことがある。
長く繰り返してきた戦闘の中で、腕力は大の男にも引けをとらず、射撃の精度はどの弓兵にも負けなかったという。 彼女の矢を避けるのは至難の業だ。
パン、と乾いた音と共に矢が飛ぶ。しかし矢が到達するよりも早く、リオンは杖を盾に変えて矢を弾いた。 将軍の舌打ちと共に、二発目・三発目が飛ぶ。しかし、この盾は数発のロングボウで壊れるほど脆弱ではない。
構えた盾の横からわずかに顔を出し、敵を覗く。ディーナ将軍の姿かたちを借りた魔物は、リオンとは別方向に矢を番えていた。 誰に狙いを定めたか、リオンは気付いた。
「よけて!ユーリさん!」
矢が飛ぶ。ユーリが気付き、武器を構えなおそうとした。
しかし、遅かった。矢は簡単に彼の軽装を突き、左胸を貫いた。
声を発する間もなく、ユーリはぐらりと身を崩し、地面に倒れた。石畳に赤が広がる。
「ユーリさん……!」
リオンの頭から、一気に血の気が引いた。思わず駆け寄る。
さっきまで生きて、笑っていた人が、仲間だった人が、こんなに簡単に死ぬものか。 きっとまだ息がある。いま手当てをすればもしかしたら。いや、きっと。
「リオン、駄目です!今は盾を!」
レイスの声に耳も貸さず、リオンは仲間のもとへ駆ける。 横たわったユーリの肩に手を置こうとしたその時。
視界が揺れた。
血の気の引いた白い肌色が。ユーリの服のベージュが。石畳に広がった赤が。傍らに生えた雑草の、茶と緑が。 色々な色が滲んで、溶けて、混じりあって、濁ったグレーの一色になっていく。
眩暈に似た感覚を覚え、思わずリオンは頭を抑えた。
いったい何が起きたのか分からぬまま、気がつけば視界は安定を取り戻していた。
地面に倒れこんだユーリの姿が、ふたたび像を結んでリオンの目に映る。 周りを見渡せば、夜の色に染まった見覚えの無い街が広がっていた。
大通りの両脇に整然と並んだ家々。そのどれもが立派な造りをしており、高々と夜空へそびえ立っている。 リオンの前後に延びた通りは遠くで城壁へと伸び、その向こうには森に覆われた山が見える。 レイスも、困惑した表情であたりを見渡していた。
さっきまでの廃村は見る影もなく、また、クラウンもどこかに姿を消したようだ。
「何、これ……」
「私にも、何が起きたのか……」
レイスはつぶやいた後、はっと気が付きユーリに駆け寄る。ユーリの首に手をそっと当てるが、数秒ののち離した。
そのとき、遠くで声がした。
「リオンちゃん!レイス!」
聞き覚えのある女性の声。ライラが、街の裏通りから姿を見せた。
国軍魔導師団の黒い服装に、セミロングの赤い髪は良く目立つ。彼女は手の杖を振り、こちらに合図しながら駆け寄ってきた。
駆け寄る途中で、ユーリの姿に気が付いたようだ。快活な表情が一転し、曇る。 「何がどうなってるの……ユーリは……?」
「ユーリは、クラウンの攻撃に倒れました……。その直後に景色が突然変わったのです」
「そう……」
仲間の訃報を聞き、彼女は視線を伏せた。
一瞬の沈黙。
仲間の一人は倒れ、敵は消えた。自分たちがいるところはどこなのか見当もつかない。 自分たちの身に起きている事象を、だれひとり説明できなかった。不安と思考を各々が脳内で巡らせる静寂を、ふと、リオンが破る。
「……とりあえずここがどこか、他の人に聞いてみませんか? 見た感じ大きい町みたいだし、誰かいるかも」
「……そうね。まずは情報収集しましょう。家は周りにいっぱいあるんだし、誰かしら居るでしょ」
「じゃあ、2階からうっすら明かりが見えるから……まずはあの家に」
リオンはそういうと、真正面の家を指した。
*
ドアノブに手をかけると、たやすくノブは回った。
鍵がかかってないことを怪しく思いながらも、リオンはドアを開ける。と、むせ返る鉄のにおいが鼻を突いた。
「うっ」
「酷いニオイ」
女性二人が顔をしかめる。リオンはさっき嗅いだばかりのにおい。 明らかに、血のにおいだ。
その横で、レイスはためらいもせずに室内へ押し入った。
「相当な量です。誰か負傷しているかもしれません。二人は二階をお願いします」
レイスに言われるまま、リオンとライラは二階への階段を上がる。
においは一段ごとに、強さを増す。リオンの脳内で、ユーリの最後の姿がフラッシュバックする。 もしかしたら。最悪の光景を想像し、思わず最上段の一段手前で足が止まった。
それを見たライラが、リオンの後ろから頭をなでる。
「よしよーし、ここまで頑張ったね」
わしゃわしゃと、二つに結んだ金髪がくしゃくしゃになるのもかまわずに、ライラは14歳の少女の頭をなでくりまわす。
「え、ちょっ! 何ですかいきなり」
「あとは、年上のおねーさんにまかせなさい? 怖いものは素直に怖いって言っていいんだから」
ぽんぽん、と仕上げに軽くリオンの頭に手を置き、ウインク。
死と隣り合わせの、焦燥。そして、味方の死を間近で見てしまった恐怖と、無力感。 重たすぎる荷物を抱えている事は、分かりきっている。 リオンはこみ上げてきたものを堪えて、素直に頷いた。
階段を上がって、ライラは右のドアを開ける。 そこは寝室のようだった。 室内のベッドの隅では、男性が床にしゃがんでがたがたと震えている。 足元には血だらけのシーツ。ベッドの上には、真っ赤に染まった子どもの死体。
ライラの背中から顔を出し、リオンは息を呑んだ。最悪の事態が、起こってしまっていた。
二人の姿を見た瞬間、男はビクッと身を引いた後に叫んだ。
「お、お前なのか!?」
「え?」
「お前だろう、娘と妻をやったのは!」
「あたし?」
突然指差しで怒鳴られ、ライラは怪訝な返答をする。男はよろよろと立ち上がった。
「どうやった?その杖で術でも使ったか? どうして娘と妻をやった!」
「待って、ちょっと落ち着きなさいよ!」
リオンも加勢する。
「そうです、私達あなたを助けたいの!」
「黙れ! いきなり……いきなりだぞ!」
「なにがいきなりなのよ!」
「シラを切るんじゃない! 娘も妻も、いきなりオレの前で真っ二つになっ
瞬間。
男の体に、縦に赤いラインが浮かぶ。頭頂から、定規で線を引いたように精緻な線だった。 赤いラインは一瞬で液体になり、あたりに鉄のニオイを撒き散らす。 そして、真っ赤な血しぶきを飛ばしながら、男の体は真っ二つに切断された。 左右にぱっくりと割れた男は、ベッド上の娘の死体に重なり合うようにして倒れこんだ。
あまりに非現実的な光景を目の当たりにして、リオンとライラは絶句する。 体中の血の気が引いていく感覚。充満した生臭い鉄のニオイがそれに拍車をかける。
「……この光景、確か……」
ライラが震える声でつぶやく。その言葉を、リオンは聞き逃さなかった。
”確か”?
リオンがそう問おうとしたとき、後ろから階段を駆け上がる音が聞こえた。
振り返ると、レイスが切迫した表情で階段を駆け上がってきた。
「ライラさん、リオン!下の階で女性が倒れ……」
室内の光景を見たレイスは、そこで事態を察したらしく言葉を止めた。
「下の階でも、女性が一人、同じ状態でした」
おそらく、先ほど言っていた”妻”だ。 ”娘と妻”と言っていたから、この家族は全員亡くなったのだろう。
自身でも驚くほど、冷静な思考をリオンはしていた。 レイスが来たことで安心したのか、それとも人の死を目の当たりにすることに自分が慣れすぎてしまったのか。
どうしよう。この先、どうすればいい? 彼女は保たれている思考力を全力で働かせる。
突然体が二つに分かれて死ぬなんて、魔法か何かを使わなければ出来ない。 ということは、この家族を無残な方法で殺した”誰か”が、きっと――
くすくす、と、笑い声が聞こえたのはその時だった。
3人がハッと顔をあげる。声がしたのは、窓際の方。 リオンたちがそこで見たのは、一人の少年だった。
3人の視線を浴びながらも、少年は尚微笑を絶やさない。 年は10歳くらい。髪はショート。服装は長ズボンと、シャツにベスト。ごく一般的な普通の少年だった。 2つの点を除けば。
彼は、まるでゴーストのように宙に浮いていた。 年下のような顔つきなのに、自分より高い目線で見られている。そのことにリオンは違和感を覚える。
そしてもうひとつの点。 彼は、頭から靴の先まで、グレーに染められていた。 まるで白・黒・灰色の絵の具で描かれた肖像画のように、彼には”色”がまるで無い。
明らかに普通ではない外見。そして、この凄惨な状況の中での笑顔。 3人は、あまりにも場違いな少年の様子に戦慄すらおぼえた。
かすかに聞こえる、少年が嗤う声。それ以外は何の音も無い重たい空気を、レイスの一言が破る。
「ここから逃げます」
「えっ?」
「いいから、早く!」
そう言うや否や階段の方へ振り返り、走るレイス。
「ちょっと、待って!」
リオンとライラが慌てて追う。
リオンが、階段を下りるライラに続こうとしたその時、後ろで声が聞こえた。
「君は」
思わず振り返る。
「君たちだけは、見えるんだね」
少年が、どこか憂いの残る笑顔で、リオンを見ていた。その右手は、こちらに差し出されている。
リオンは立ち止まる。そして、意を決して少年の方に向き直った。 両手は、しっかりと杖を握る。臨戦態勢であることを相手に示す。
「あなたは、誰。おじさんたちを殺したのは、あなた?」
「知らないほうが君のためだと思うよ? ねえ……リオン!」
悲しげだった眼差しが、一瞬にして強い光を帯びた。 絶好の獲物を見つけたときのように、少年の表情はするどい笑みに変わる。
差し出された手が青白く光ったのを見て、リオンはとっさに後ろによける。
直後、右横の壁が見えない刃で切り裂かれたように鋭くえぐれた。
「動かないでよ!せっかく本気出してるのにさ!」
左手が、青く光る。
――もう一発、来る!
また一歩後ろに避けようと下げた右足は、
階段を踏み外した。
少年の頭を、窓を、梁を、天井を視界が通り越す。 リオンの体は重力にしたがって、階段の上を急降下した。
大きくて重たい衝撃のあと、彼女の視界は暗転した。
Ⅰ-2
目を覚ますと、こげ茶の天井が見えた。
頭が重い。腰も、肘も痛い。腕をあげると、左手に青あざが見えた。 リオンは上半身を起こす。どうやらここはベッドの上のようだ。 内装からして、宿の一室らしい。
部屋を見渡すと、横のテーブル越しに話すレイスとライラが見えた。 何を話してるんだろう。ぼんやりとそう思ったとき、レイスがこちらに気付いた。
「リオン。具合はどうですか?」
二人が立って、ベッドサイドまでやってくる。
「うーん、色々いたい」
まだ眠くて、頭がうまく回らない。少年のこと、ユーリのこと、聞きたい事は山ほどあるが言葉が出てこなかった。
「そりゃそうよ。覚えてる?あんた階段からおっこちたのよ。あんたを担いで、あの少年から逃げてきたんだから」
そういえばそうだっけ。色々ありすぎて、全部がごちゃまぜになっている。
何から起きたのか、順番にしていこう。 ユーリさんが死んで、それで、おじさんが死んで、それから……。
ライラが聞く。
「どこが痛い?」
どこもかしこも痛かった。左手はあざが出来てるし、腰も痛む。 肘も、もしかしたらあざになってるかもしれない。
でも一番痛いのは、
「……胸。胸の中が、押し潰されるよう……」
――ユーリさんは仲間だった。なのに、助けることも盾で守ってあげることも出来なかった。
――おじさんは、家族二人を殺された。真っ二つになる二人を見て、何を思ったんだろう。
また、何も出来なかった。
ライラがリオンの表情を察し、おもむろに抱きしめたとき、リオンの中で張り詰めていた糸が切れた。 リオンは、ライラの胸の中でしばらく嗚咽をこらえていた。
*
「私達が追っている”クラウン”は、あのグレーの少年に変化したようです」
軍支給の保存食で出来た夕食を囲み、レイスが説明する。
「え、でもクラウンってディーナ将軍に変身していたんじゃないの?」
「ええ。ユーリ少佐が、死ぬまでは」
リオンの問いに答えつつ、レイスは卓上に置いてあった羊皮紙を見せる。 本ほどの大きさのそれには、びっしりと書かれた文字。
その文面は、リオン達討伐隊の派遣要請を示すものだった。
「3日前に渡されたこの要請状。要約すれば、”廃村にクラウンが出現したため討伐せよ”ということです。 ですが、なぜ城に帰還したばかりの私と、王国軍でもないリオンが隊に編成されたか……知ってましたか?」
「ううん。私もずっと不思議には思ってたけど。どうして?」
「それは、クラウンの性質の特殊性です」
「性質って、変身能力のこと?」
レイスは頷く。
「クラウンは、敵が一番恐れるものに変化する。魔物の中でもなかり特殊な性質を持つ故に、有効な戦闘方法や出現地域の分布など、 不明な点が数多く残されています」
「うん」
「剣と魔法の両方を主の武器として扱える私と、未知の武器を持つリオン。 私達が選ばれたのは、クラウンの性質を更に解析する意義があったのです。 今までのクラウンは姿のみ変化していましたが、今回相手にしているクラウンは、どうやら周囲の景色までも再現してしまうようです」
「景色?どういうこと?」
「リオンちゃん」
水を飲み干したライラが、会話に加わる。
「例えばの話よ。リオンちゃんが昔ハチに刺されたことがあって、それ以来ハチがトラウマだとしましょう。 普通のクラウンはハチに変身してそれで終わりだけど、私達が戦ってるクラウンは、あなたがハチに刺された状況そのものを再現できるのよ。 刺されたときの周りの景色とか、その時暑かったか寒かったか、とか。ど? 怖さ倍増でしょ?」
「確かに」
リオンは頷く。実際、虫に関するトラウマ体験を昔経験したことがある。あの状況そのものを再現されたら、 正直言って立ち直れる気がしない。
リオンはレイスの方に向き直る。
「じゃあクラウンは今、トラウマの状況そのものを再現してるの?」
「おそらくは。クラウンがユーリ少佐と戦っていたとき、アレはユーリ少佐の記憶の中からディーナ中将のことだけを取り出し、変身しました。 しかしユーリ少佐が死んだら、読み取る記憶が無くなってしまう。だから、クラウンは別の人のトラウマ風景を読み取ったのです」
「今度は周りの景色までちゃーんと読み込んで、ね」
狡猾よねえ、とつぶやくライラの隣で、リオンは納得した。 おそらくあのグレーの少年がクラウンで、この町や周りの人々は”景色”に含まれるのだろう。
リオンは、この景色やあの少年に見覚えはない。つまりクラウンは、レイスかライラのトラウマを読み取って、町ごと変化することで攻撃を再開した。
今目の前にいる二人のうち、どちらかは凄惨なトラウマを抱えているのだ。 そして、それと今、向き合うことを余儀なくされている。
――私も泣いてなんかいられない。頑張らないと。
「あのね、リオンちゃん」
「なんですか?」
「この風景ね、私の記憶から読み取ってるんだよね」
「え……」
あまりに突然のライラのセリフに、リオンはかける言葉を失う。
「この町すごく見覚えあるなあと思ったら、私が13歳のときまで住んでた町だったんだ。 あの頃と、町並みはぜんぜん変わってない。ホント、あの時のまんまなの」
「それじゃあ、さっき起きた出来事は」
「私が体験した事件よ」
ライラは、スプーンを置いた。
「私の故郷は、今から十年前に一日で壊滅したの。生存者は十名足らず。私はその中の一人」
ライラの一言は、衝撃的だった。
――ここは結構規模の大きい町のはず。それが、一晩で、たった数人以外みんな死んだって言うの?
「なんで、いったい何が」
レイスが、その問いに答える。
「もともと、アルファルドや近隣の国では二,三年に一度みられるんです。町や村の人が、ほぼ全員切り殺される事件が」
「えっ……」
リオンは言葉を失う。街が壊滅する事件が、二,三年に一度も?
「最初は、この国の北部の村の人間が全員惨殺体で見つかりました。いつ起きたかは定かではないですが、少なくとも300年以上前かと」
「300年!?そんなに前から?」
レイスは頷き、続ける。
「それ以降、数年に一度のペース――多いときは半年に一度、村や町の人間が襲われる事件が起きています。犯人を見たという証言はなし。 切断面が異常なほど滑らかで、普通の刃物では出来ない傷跡があるために、魔法によって惨殺されたものと考えられています」
「で、毎回必ず一人生き残りがいるのよね。どの村でも、どの町でも一人だけ。 みんな口をそろえて『目の前で人が真っ二つに切れていった。あれはきっと人には見えない悪魔の仕業だ』って言うのよ」
「最後の事件が起きたのが、10年前です。その時の生存者は8名。それ以降、事件の発生は止んでしまいました。 ……まさか、ライラさんがその事件の生き残りとは……」
話が終わったところで、リオンがライラに聞く。
「じゃあ、あのグレーの少年は会ったことがあるんですか?」
リオンの予想とは反し、ライラは首を横にふった。
「いや、知らないわあんな子。見覚えもまったくないのよね。それともどっかで会ったのかしら?」
ライラは首をかしげる。そして、リオンも。
クラウンがライラの記憶を読み取っているのなら、ライラの記憶にないものは普通読み込めないはずだ。 じゃあ何故、クラウンは誰も知らない少年に変身することができたのだろうか。 ライラが思い出せていないだけなのか。
悩むリオン。その隣で、ライラが立ち上がった。
「とにかく、今は悩んでてもムダだわ!犯人があの少年だってことは分かった。とりあえずあの少年を倒して、クラウンをとっちめましょ!」
「そ、そうですよね!魔物を倒す、いまはそれだけ!」
リオンも思わず立ち上がる。
「一緒に戦うわよ!」
「おー!!」
宿の天井へ高く突き上げた二つのこぶしを、レイスは若干の苦笑いで見守っていた。
Ⅰ-3
翌朝。
昨日と同じく、空には厚い雲がかかる。気持ちの晴れない曇天の下で、三人は町外れの墓地にいた。 墓地の一角を借りて、三人はユーリの遺体をそこに埋めた。
ここは記憶を再現した町。クラウンを倒し周囲の景色が廃村に戻ったとき、この墓とユーリの遺体がどうなるかは予想がつかない。 それでも、三人はクラウンとの戦いよりも優先してユーリを弔う理由があった。
クラウンと、次にいつ遭遇するかはまったく予想できない。 この次の瞬間には、あの冷笑とも取れる微笑が目の前に現れるかもしれないし、もしかしたらそれは一週間以上先になるかもしれない。 いつ達成できるか分からない討伐より、ユーリの遺体を先に弔っておきたかった。区切りをつけたかった。
ユーリの生と、残された自分たちの気持ち、に。
三人はしばし黙祷を捧げ、おもむろに顔を上げた。
「――さて! 気を引き締めていかないとね」
ライラが言う。
リオンも、その言葉に頷く。 残ったこの三人で、あの少年を倒さなければいけない。
「ライラさん、強いんですね」
「え?」
「だって、今自分が一番怖いこと見せられてるのに、ぜんぜん悲しい顔を見せないですから」
「何言ってるの! あなただって同じじゃないの」
リオンは首をかしげる。
「同じ?」
「レイスから聞いたわよ。あんた……小さいときに火事に遭ったって」
「勝手に話してすみません」
「自分が火事にあったのに、それでも構わずレイスのこと助け出したんだってね。あなたもよっぽど立派じゃないの」
「そ、そんなことないです!あの時はホントに無我夢中で」
リオンは赤面した顔を、ぶんぶん横に振った。
ライラは昨日と同じように、ぽんぽんと手を頭に置く。
「あんなにすごい体験したのに、たった一回しか泣いてないものね。えらいぞ」
恥ずかしい。これじゃまるで子どもだ。いや、まだ子どもなんだけど。
……あの少年も、こんな風に普通の子どものように接してくれる”誰か”がいたのかな。
リオンは昨日相見えた彼の表情を思い出す。 ”君たちだけには、見えるんだね”と、あの言葉の意味。
何故自分の名前を知っていたのか。
何故あんな姿をしているのか。
ライラは彼のことを知らないのに、なぜ変身できたのか。
普通の人間ではない事は、分かりきっていた。しかし、彼には謎が多すぎる。
そんなことを考えながら、リオンたちは墓地を後にした。
*
どこへ行こうか。どこへ行くべきか。
少年が出現する時間も場所もまったく見当がつかず、三人はしばし街中をさまよう。
その時、レイスがふとリオンとライラに聞く。
「お二人は、ゴーストの概念を信じますか?」
「ゴースト?」
「何、急に」
二人のきょとんとした顔を見て、レイスは付け足す。
「いえ、あの少年は外見がゴーストそっくりのようにみえたので」
リオンがもといた世界にも、ゴーストの話はあった。
人の体と魂は魔力で動いていて、体に大きなダメージを負ったり魔力がなくなってしまうと人は死ぬ。 その際、体から抜け出すのがゴースト。体から抜け出たゴーストは女神の下で、扉を縛る鎖と錠前の点検や手入れをするのだとか。
話は半信半疑だが、基本的にリオンはゴーストを信じていた。 父や兄が扉の守りに関わる仕事の合間に、自分や母を見守ってくれていると思うと、ウソの話でもなんとなく嬉しかったから。
「レイス、私はゴーストの話信じてるよ」
「あたしは信じてないほうかしらね。魔導師の身でいうのもなんだけど、そういう物理的根拠のない話はあんまり」
レイスはどうなの?というリオンの問いに、彼は首を横に振った。
「信じてません。いえ、信じたくありませんね」
「どうして?」
「死後に誰からも見てもらえず、誰にも声が聞こえないままずっと存在するのは……ある意味残酷ですから」
そう答えた後、彼は口をつぐんだ。
*
やがて大通りへ出て、狭かった視界が開けた。その先に、一人でたたずむあの少年を見つけた。
「ちょっと、あんた!」
最初に声をかけたのはライラ。彼女の声に、少年は振り返る。
「ああ、おはようお姉さん達。昨日はどうしたの? 逃げちゃうなんてヒドいじゃないか」
「あんた、人の家族や友達を散々殺しておきながらよくも!」
くってかかろうとするライラを、リオンが制する。
「君にききたいことがあるの」
「ちょっと、リオンちゃん」
リオンはライラの一歩前にでる。少年は昨日とまったく変わらない微笑を浮かべて、言った。
「質問は聞くけど。答えは聞かない方がいいんじゃないかなあ」
「どういうこと?」
「リオン。危ないですから下がって」
レイスがリオンの隣に並ぶ。左手は、剣の柄を握る。
三者三様の沈黙が降りる中、少年はまた、くすくすと笑った。
「どうするの? 質問、するんじゃないの?」
「質問は……不要です!」
言い終わると同時に、レイスは地を蹴る。 柄を握る左手に力を込め、彼は少年の懐へと突っ込んだ。その勢いで剣を引き抜く。
少年は容易く横へ避け、すれすれでかわす。 レイスは振り返り、敵を視界に捉えなおした。少年は尚も嗤っている。 宙を薙いだ切っ先を引き上げ、真下へ振り下ろす。
長剣の切っ先は、たしかに少年を捕らえた。そう思えた。
しかし刃は少年の体の中を、すっ、と通り抜けた。
リオンやライラからみたら、少年はレイスの剣に切り裂かれたように見えただろう。 しかし、少年は何事もなかったかのように無傷で浮いている。
レイスがそれまで少年に向けていた刺すような視線が、少しだけ揺れた。
「まさか、見えるけれど触れないとは……」
悪戯に成功したかのような笑顔を、少年は浮かべる。
「びっくりした?」
「いいえ、全然?」
その答えを返したのは、ライラだった。
少年の視線がレイスからライラに移った瞬間、彼女の杖から炎の渦が向かってきた。 レイスは咄嗟に後ろへ下がる。炎は少年を飲み込んだ。
激しく重苦しい音を立てて、炎はしばらく燃え続けた。 しかし火の勢いが収まるにつれて、中から先刻とまったく変わらぬ少年の姿があらわになっていった。
「ビックリするなあもう。仕返しにしても、ひど過ぎない?」
焦燥の声を隠しきれぬまま、ライラは言う。
「ちょっとぉ……折角がんばって詠唱したんだから少しは効きなさいよね……」
「やだもん。熱いのは嫌い」
ぷう、とむくれる少年の横で、レイスはすでに詠唱を始めていた。 彼の声に気付いた少年も、同様に詠唱する。
次の瞬間。
レイスの剣と、少年の左手に、双方に青く光る水流が浮かぶ。 それは互いの敵を切り裂かんと、勢いを伴って放たれた。 水流は鏡写しのようにまったく同じ形、同じスピードでぶつかり合う。
やがて互いに打ち消し、やがて二つの攻撃は相殺された。 はじけ飛ぶ水滴。水しぶきがわずかな陽光を反射する中で、銀の瞳とグレーの瞳は敵対のまなざしを向けている。
リオンは、固唾を呑んで闘いの行方を見守っていた。 杖は、両手でかたく握っている。しかし、今の状況で自分が戦闘の中に割って入ればレイスの邪魔になる。 それが”見守る”ことを選んだ大きな理由であるが、もうひとつ理由があった。
少年には触れないし、魔法も効かない。 レイスの剣と、ライラの魔法を通さなかった彼を、どうやって倒せばいいのだろう。 勝機がまったく見えなくなってしまったこの戦況で、自分が闘いに参加する事は果てしなく無意味で、無謀なことのように思えたのだ。
倒す方法が見つからない。 それは、即刻”死”に繋がりうる事態であることを、リオンは理解していた。
そこから生まれる焦燥と戦慄は、おそらくレイスも感じているのだろう。 レイスは少年との間をあけるべく、一歩ずつゆっくりと後ずさりする。レイスのすぐ後ろには、民家。 家の外装に、三人は見覚えがあった。そして、家の内部が惨憺たる光景だったことも覚えている。 その家の主は、昨日リオンとライラの目の前で切り裂かれたあの男だ。
レイスの背が民家の壁についたと同時、レイスはうつむいて剣を鞘に収める。 少年はせせら笑う。
「どうしたの? もうおしまいにしちゃっていいの?」
左手が、青く光りだし、少年が水流を放とうと身構える。 しかし少年の攻撃より先に、レイスの詠唱は完成していた。
レイスが背にした家の中から、強い青の光が差す。
彼がしゃがむと同時。家の内側から獰猛な水流が、巨大な矢のように少年めがけて襲い掛かる。 水は家を内側から破壊し、おびただしい数の木片を伴って少年の視界を奪う。
レイスは、その瞬間を見逃さなかった。 彼は駆け出し、リオンとライラの手をとって裏路地に逃げ込む。 そして自らの足音を消すために、振り返りざまに数方向から水流の追撃を少年に与えた。
水流が完全に止み、少年が静寂に包まれた中で辺りを見回す頃には、レイスたちは遠くの路地へと逃走を終えていた。
Ⅰ-4
この町に連れてこられてから、二回目の夜が来た。 夜を明かすのは、昨日と同じ宿。部屋も同じである。 リオンとライラは一階の厨房で夕食の支度を、レイスは二階の部屋にいる。
「ねえ、ライラさん」
スープをかき回しながら、リオンはライラに訊く。
「どした?やっぱ味濃すぎかな、それ」
「ううん、料理の話じゃなくて」
きょとんとした顔で、ライラは隣のリオンを見つめる。リオンは鍋の中のスープを、いや、どこともいえない一点を見つめている。
「お昼の闘いのときから、ずっと引っかかってることがあるんです」
「引っかかってること?」
「ライラさん、あの男の子のこと、ホントに覚えてないんですよね」
ライラは腕組みして、思い出そうとする。
「うーん……うん。やっぱ思い出せないわ」
「覚えてないんじゃなくて、本当にライラさんが会ったことのない人だったんじゃないかなって思って」
「まあ、私もそれを思ったのよね。でもそうすると、クラウンは私の記憶を読み取ってるのと矛盾するじゃない?」
リオンは、ライラが投げかけた疑問にしばし答えなかった。ためらっていたからだ。
これから自分が話す事は、ただの憶測だ。しかもそれは、当たっていても外れていても今後の三人の関係に傷を残す。 もしかしたら、その傷がずっと残るかもしれないのだ。
でも、この並行線上を行く状況を打開するにはこれしかないように思えた。
リオンは、口を開く。
「クラウンは、ライラさんの記憶を読み取ってるんじゃないんだと思います」
ライラはしばらく言葉を失った。
「え……え、いや待って! じゃあリオンちゃんの記憶でも読んでるっていうの?」
リオンはもちろん、否定する。
「クラウンが今変身してるグレーの男の子って、村や町の人たちを殺してる犯人ですよね?」
「そうね」
「犯人を見た人は今まで一人もいない、って昨日レイスとライラさんが話してくれました。 だとすると、クラウンが犯人に変身できるのは、クラウンが”犯人の”記憶を読み取ったときだけだ……って、さっき考えたんです」
「まあ誰も犯人を見てないってことは、犯人の記憶がそもそも誰にもないわけだし。考えてみればそうね」
口に手を当て、考えながらライラは話しているようだった。しかし彼女の表情が段々と青ざめていくのを、リオンは見ていた。
ライラの中でも、考えが繋がったようだった。
クラウンは、リオンとライラ以外の人間の記憶を読んでいる。そしてその人間は、幾つもの命を奪った犯人だ。
ライラの声は、震えていた。
「つまり何よ、町や村の人間を300年以上の間殺して回った犯人は、」
「何の話をしているのですか?」
聞きなれた穏やかな声。
声の方向にリオンとライラが振り向くと、階段を降りるレイスの姿が見えた。 レイスは、普段と変わらない微笑を向ける。あの少年と、同じ笑みを。
リオンは無意識に、左手を自身の右手首にかける。そこには、腕輪に変形させた杖がある。 レイスはその間にも、階段を降りきってこちらの方へ向かってくる。 いつもなら。いつもなら、頼るべき姿に。安心する微笑に、警戒している自分がいる。
「攻撃の、仕方がね」
震える声で、リオンは言う。
「攻撃の仕方が、まったく同じだったの。水で切り裂く方法が」
レイスは口を開かない。
「レイス。クラウンが読み取ってるのは、レイスの記憶だよね」
彼は黙ったまま。
「レイス。全部知ってたの?自分が犯人で、あの少年は子どもの頃の自分だって。全部知ってたのに話さなかったの?」
ありえない。レイスがそんなことするはずがない。しかし、こうでないと辻褄が合わない。
水を打ったように静かな空気が、積もり始める。 重苦しい、これまでにない張り詰めた沈黙だった。
「……私と彼、面影は残っていましたか?」
その一言は、リオンとライラの意表をついた言葉だった。
返答に詰まる二人を見て、彼は続ける。
「髪型も口調も違うから、うまく誤魔化したまま彼を倒せるかと思っていたんですが……。 参りましたよ、何の攻撃も通じないんですから」
「彼の姿が、リオンたちにも見えてしまったのが最大の誤算でしたね。 おそらく、あのクラウンは変身した対象の性質を微妙に変えることが出来るようです」
「もしクラウンが過去の私そのままに変化してしまったら、私もリオンもライラも彼の姿を捉える事はできないはずですから」
――何を、言っているの?
リオンは、レイスが目の前で発するセリフを理解できずにいた。 言葉が、頭の中で捉えることのできないまま零れ落ちていく。
丁度、手の平で汲んだ水のように。
「ライラが、十年前私が起こした事件の生き残りって知ったときは流石に驚きましたよ」
「やっぱり、あの時一人残らず殺しておくべきだった」
その瞬間、リオンの隣でスープの鍋が飛んだ。 火にかけられていた鍋のスープは、レイスの手前の床にぶちまけられる。
リオンが驚いて横を見ると、鍋を倒したライラが獣の様な視線でレイスを睨みつけていた。
「何よ、なんなの!何でそんなこと……家族を、友達を何で殺したの!」
「理由を知って、どうするというのですか?」
「どうにもなんないわよ!知ってるわそんなこと!だけど、あたしが何のためにこの十年生きてきたと思ってるのよ!」
ライラは、吠えるように言葉をぶつける。
「犯人が憎くて、悔しくてたまらなくて、だから犯人を捜して殺すために魔導師団に入ったのに! 魔法の研究もずっと続けて……。 なのに何で!? なんで同じ国軍の、あんたがそんなこと! 国軍に入ったのは、殺人衝動に理由付けするため? なんなのよ!」
ライラは激昂し、すべてを吐き出し終わった。それでも、レイスを刺す眼差しの鋭さは変わらない。
味方だと思っていた人間が、崩れるように得体の知れない敵になってしまったこの状況に、リオンは恐怖した。
信じていたものに裏切られた。既知のものが未知になってしまった。
コインがすべて裏返しになったように、”知っている”ことが”分からない”ものへ変わってゆく。
――これ以上、彼の何を信じればいいの?
レイスは微笑み、そして言った。
「これ以上話すべき事はないでしょう。リオンの疑問も無事に解決したことですし」
そして、踵を返し階段の方へ向かう。 呆然としたままの二人の方を振り返り、彼は別れ際に言った。
「これから、クラウンとの闘いは二対一ですね。どうか、ご武運を」
それは、レイスがもう永遠にこちらの味方にならないことの宣告だった。
絶望の中に、彼の足音だけが遠く響いた。
*
厨房の火を消して、もう一時間にもなる。 リオンとライラは、互いに何も言わず座り込んでいた。
あの後、レイスがどうしたかは不明だった。
厨房と宿の玄関は、別方向にある。足音に気がつかなければ、人の出入りは厨房からは分からない。 まだ部屋にいるかもしれないし、もしかしたら、すでに荷物を持って宿を出た可能性もある。
しかし、今の彼と会う気力は二人には残っていなかった。
クラウンが変身した少年は、子どもの頃のレイスだった。 そして、彼は村や町を襲い人を殺し続けていた。 その事実だけで、二人を打ちのめすのには十分だった。
リオンの中で、去り際に彼が残した言葉が突き刺さる。
”これから、クラウンとの闘いは二対一ですね。どうか、ご武運を”
レイスが味方を去った、と受け取れる宣告。
――クラウンと戦う気力なんて、もう無いよ――
抱えた膝に顔をうずめると、火照った目頭に涙がまたこみ上げてくる。 いつもは、どんな状況でもレイスがいたから前向きになれた。
だけど今は彼はいない。
第一、倒す方法がなくなってしまったクラウンを二人だけでどうやって倒せというのか。 ”ご武運を”なんて、皮肉にしか思えない。 ユーリが亡くなって、クラウンが記憶を読み取る対象を変えてから、キズ一つ与えられなかったではないか。
ユーリが、死んでから……。
リオンは、ハッと顔を上げる。そして、驚くライラの方は見向きもせずに部屋へ走り出した。
レイスの部屋のドアを開ける。中は無人だ。 部屋の中央に、あるものを見て、リオンは確信した。
「やっぱり……」
そこには、鞘に収められた剣と、鎧一式。
戦う者の命を守るものが、そこに置き去りにされていた。
リオンは迷わずに剣を取り、そして、走り出す。 ドアを開け、宿を出て、町の大通りの方へ。
レイスをもう一度信じるため。