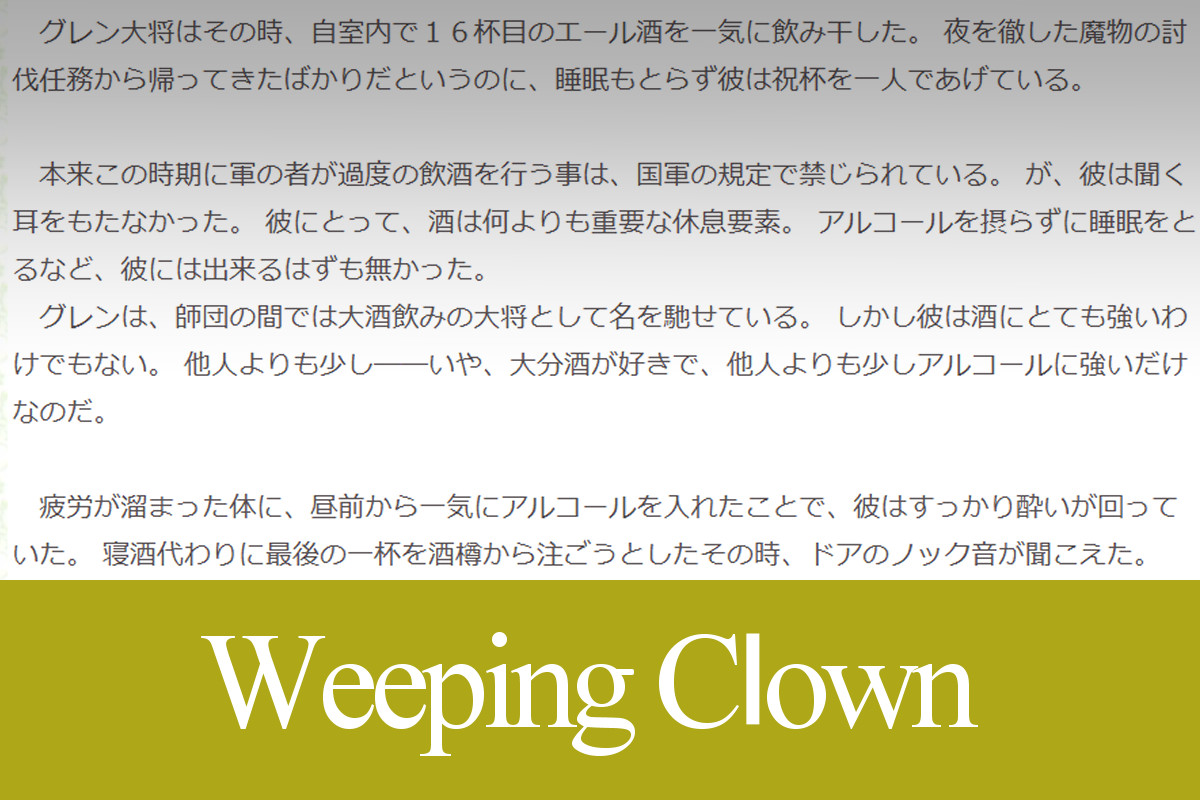Ⅱ-1
町を歩く。夜の帳が下り、家から差す明かりは無く、唯一の頼りの星空も時折雲に隠れてしまう。
しん、とした町の中を、レイスは歩く。
鎧の下に着るための服は、丈夫で厚い。寒さはそれほど感じず、鎧を着慣れている身としてはかえって身軽すぎて落ち着かない。
鎧も、剣もない。
戦うことを完全に放棄した彼は、歩きながら過去の自分の記憶を思い返していた。
*
何年前に生まれたか。そんなことすら、レイスは覚えていない。
ただ、アルファルド王国の領地が内戦により二分されたのが、約450年前。 その時の戦の様子はかすかに覚えているから、少なくともそれより前だ。
どうして生まれたのか。そんなことすら、レイスは知らない。
ただ、生まれたとき魔導師のような服装をした男女が周囲に何人もいたことを覚えている。 棚と机の上には魔道書。床には魔方陣。
おおかた、”魔力だけで人間をつくれるのか”実験をしてみた。そんなところではないだろうか。 自分はその”実験の成果”だ。
人間を人工的に作りたかったのなら、実験は完全に失敗だ。
なぜなら、生まれてきたレイスの姿を認識できた人は、誰一人としていなかったのだから。
生まれてきたとき、レイスには知能があった。言葉を使い、物を考え、感情を出す。それを形容するのに一番近い言葉は、”魂”だろう。 彼にはそれがあった。だけど、彼の姿が見えたものはいない。声を出しても、聞こえた人はいない。 物を触ることも出来ない。触ろうとすると、彼の手は物を通り抜けてしまうのだ。
彼には、魂はあったが肉体が無かった。
彼は、生まれながらにしてゴーストとなんら変わりない状態で、孤独に存在することを余儀なくされた。
*
生まれてからずっと、苦痛でしかなかった。
誰も自分ことを見てくれない。
大声を張り上げて叫んでも、誰にも聞こえない。
物をつかんで、壊して、自分のことを見てほしかった。でも、それも叶わない。
自分の存在を、自分以外に誰一人分かってくれなかった。
だれも自分に気付かない。
周りの人間が羨ましかった。お互いの目を見つめ、声で会話して、手で触れる。 嬉しそうに会話する人たちを見た。頭をなでられる子どもを見た。キスをして愛を受け取りあう恋人たちを見た。 悲しいときに、一緒に涙を流す人を見た。
――僕は、それが出来ない。
羨ましかった。誰かの声が欲しい。撫でてくれる誰かの手が欲しい。愛情を伝えるふれあいが欲しい。一緒に流れる、誰かの涙が欲しい。
――見てるだけなんて、もう飽き飽きだ。僕は、僕には……。
絵画の世界を見ているかのように、彼は世界と交流することを許されなかった。 そして、ただ見ていることしか出来ない日々が延々と続いたのだ。
ある日を境に、羨望は嫉妬に変わった。 人間が妬ましく思えるようになると、彼らのコミュニケーションを邪魔してやりたくなった。
彼らの間に割って入りたい、彼らを突き飛ばしたい、彼らを……。
その思考が彼を支配するようになった。
そんなある日、机の上に置かれた一冊の本が目に留まった。 開きっぱなしのその本は、右のページに魔法陣が書かれている。魔道書のようだ。 とある攻撃魔法の呪文について解説したページだったが、内容は簡単ですぐに理解できた。
そして、近くにいる人に試しにその魔法を掛けてみた。
呪文は簡単に成功した。 手の平から生まれた水流は、目の前の人間を縦に二等分にした。
ごとん。 半身は床に落ちる。
その物体を見て、恐怖も驚愕も、感じなかった。 唯一感じたのは、達成感。それだけだ。
――僕の魔法で、人が半分に割れた。僕の、僕の魔法で!
言いようのない高揚感が湧き上がってくる。
平行線上にいた世界が。一切干渉を許されなかった、世界が。 立ち入ることの出来なかった”世界”への鍵を、ついに見つけた。
――魔法を使えば、何でもできる。切る事も、壊すことも、殺す事だってできるのだから。
やがて、人の惨殺体を見た他の人間が悲鳴を上げた。その悲鳴を聞いて、人が集まってくる。
阿鼻叫喚な状況とは逆に、楽しい気持ちが次から次にこみ上げて抑えきれない。 一人の人間を殺したことで、多くの人間が集まった。そのことが、より一層愉快にさせる。 一つの生命に干渉すれば、次々に他の人間の感情にも干渉ができるのだ。
一歩、足を踏み入れた”世界”。どうせなら足で地面を荒らしまわって、手で物を壊しまくって、自分がいる痕跡を残そう。
――僕の姿は、誰にも見えない。だけど、ほら、魔法を使って壊せば……
「僕はここにいるって証明になるでしょう?」
穏やかな微笑みを浮かべ、純粋な少年はその場の人間全員を殺した。
そして、その時の快楽と自己存在の証明を他の場所でも得るために、世界を歩き回る旅に出た。 町を見つけては壊し、殺し、自分で”世界”に傷跡をつける。 一人だけ殺さずに生かしておくのは、『悪魔の仕業に違いない』と証言する生き証人を残すため。 生存者は他の町に流れ着き、そこで恐怖におびえながら『悪魔』の存在を他の人に言って回るだろう。
この繰り返しを何年も、何十年も、何百年も行い続け、体を持たないゴーストの少年は自己の存在を他者に知らしめることに成功した。
*
レイスは歩く。
生まれたばかりの自分には無かった”体”で、両足で、歩く。
十年前――この町でまだ殺戮を繰り返していた自分を、”あの人”は変えてくれた。 ”あの人”から体を得て、道徳を得て、人の痛みが分かる心を得た。
”あの人”がいたから自分は変われた。
そして、過去の自分が許せなくなった。 人を殺してはいけない。当たり前のことを学習できた結果、レイスは過去の自分を責めた。 そして、もう二度とあんなことはするまいと固く誓い、自分自身を変える努力をした。
幼若な欲求におぼれていた過去の自分と、今の自分は違う。 レイスはそう言い聞かせるように思考をめぐらせ、歩く。 そして、裏路地の一角にたたずんでいる少年を見つけた。
「……探しましたよ」
レイスの声に、少年は微笑んだ。
目の前で浮かぶ”過去の自分”の化身は、あいかわらず無彩色の色彩でこちらを見ている。 少年は、言う。
「一人で来たんだ。じゃあ、何も隠さずお話できるね」
「あなたと話をするために来たのではないのですが」
少年は、屈託の無い笑顔で笑う。
「そうだよね。君は僕が嫌いだもの。君は僕が嫌いで、怖くて、憎いから。 僕の面影なんて残らないくらい、この十年で君は変わった。髪形も口調も性格も変えて、大人っぽくなったよね」
「過去の自分に評価されたくはありません」
「で?どうして、鎧も剣もないの? 戦う気、起きなくなっちゃった?」
レイスは沈黙した。
戦う気など、始めからない。 十年前……ライラの故郷であるこの町で”あの人”に出会ってから、自分は変わった。 いや、変わろうとした。
それまでの自分が嫌でたまらなくなった。だからこそ、自分自身から逃げるようにこの十年を生きてきた。 影のように自分の後ろを付きまとう過去の自分を振り払って、”正しい道”をひた走ってきた、つもりだ。
十年の間ずっと逃げてきたのに、こんなところで過去の自分と対峙するなんて、出来るはずも無かった。 戦って自分の心が折れるくらいなら……いっそのこと何も傷つかずに死ぬほうがマシだ。
「クラウン」
レイスは、討伐すべき魔物”クラウン”の名を呼ぶ。
クラウンは、外敵の記憶を読み取り”一番恐れるもの”に変化する魔物。 外敵が死ねば、変化が解けるのはユーリの件ですでに証明されている。 ならば、攻撃の効かない対象に変化してしまった今のクラウンを、倒す道はひとつ。
レイスは微笑む。最期くらいは、過去の自分を哂ってやりたい。
「死刑囚に武器防具は不要でしょう?」
――私が死んだ後。クラウンは、リオンとライラのどちらの記憶を読み取るのだろう。
願わくば、二人が”一番恐れるもの”に打ち勝てることを信じて。
レイスは、魔物へ歩み寄る。
Ⅱ- 2
何度切りつけられただろうか。痛みのせいで、どこに何箇所傷が出来ているかもわからない。
出血で朦朧とする意識の中、レイスはまだクラウンを見つめていた。
過去に何人も人を殺してきた。しかし、どれも一撃で体を切断してきた。 だから、自分も一撃で死ぬのだろうと思っていた。しかしどうやら、目の前の魔物は簡単に自分を殺してはくれないらしい。
脚に力が入らなくなってきた。ずるずると座り込む。 民家の壁にもたれかかり、そのままうなだれた。
おそらくこれで終わりだろう。
もし、この先リオンとライラがクラウンを倒すことが出来たら…… 彼女たちは、どういう未来を歩くのだろう。 ライラは復讐を終えて、国軍を抜けるだろうか。リオンは、一人で扉の麓へ向かうだろうか。
彼女たちのどちらも、過去に深い傷を抱えている。
見えない傷は、痕を残さずに治癒する事なんてきっとない。 でも、せめて化膿することの無いように過ぎていってほしい。
自分は、それが出来なかったから。
視界の端に、青い光が見える。
――終わりだ――
そう思ったとき、遠くから聞こえてきた足音が目の前で止まった。
顔をあげる。
そこには、二つ結びの金髪の少女の背。
「リオン……?」
盾を持っている。クラウンの一撃をはじき返したあと、彼女はこちらを振り返った。 その表情は憤りを隠し切れずにいるようだ。目も赤く腫れている。 しばらく身を震わせたまま立っていた彼女は、いきなり叫んだ。
「ばかっ!」
「えっ?」
「鎧と剣置いたままにしてたから、まさかと思ったら……。やっぱりクラウンといた! まさかホントに……」
声に涙が混じる。
「ホントに……死のうとするなんて、バカだよ……」
言葉に嗚咽が混じり、彼女はそこで泣き崩れた。
良く見ると、リオンの足元には剣もある。まさか、今のクラウンと戦うつもりで持ってきたのか。
「リオン」
まだ残っている体力で、彼女を諭す。 ここで説得に失敗すれば、クラウンの攻撃に巻き込まれて彼女も死なせてしまう。それだけは避けたかった。
「今のクラウンには攻撃が通じないんです」
「知ってる」
「だから、今のクラウンの変身を解くには私が死ぬ必要が」
乾いた音を立てて、レイスの左頬に痛みが広がる。
頬を押さえてリオンを見る。まさかこの歳で平手打ちをくらうとは。 彼女はポロポロ涙をこぼしながら体を震わす。
「なんでそういうこと言うの……。レイスはいつもそうだよ。自分ばっか危険な方に行ってさ」
リオンは、両手で必死に涙を拭う。
「レイスがホントは優しい人だって、知ってる。だからあの時も、自分のあとを追わないように”殺しとくべきだった”とか、 わざと酷いこと言ったんでしょ? 自分が犠牲になることしか考えてない!」
叱られる事は承知の上だ。こうすることが、リオンとライラを助ける最善の方法に思えたから。
リオンは続ける。
「誰も死なない方法、あるよ。レイスばかりに傷は負わせない」
「誰も犠牲が出ない方法、なんて」
「あるよ!クラウンは”怖い”ものに変化するんでしょ?なら、昔の自分を怖いものじゃなくしちゃえばいいじゃない」
そんなこと、理想論だ。レイスは思う。
十年の間必死に逃げてきた過去の自分に、いまさら向き合って克服しろというのか。
リオンは幼い頃火事に遭った。そして、そのトラウマは克服している。 だけど、偶発的な事故のトラウマと必然的な自己のトラウマは、違うのだ。
人を無差別に殺してきた昔の自分。自己顕示欲と嫉妬感情にまみれた自分。 今の自分は違う。人を守るために剣を握って、人間関係に嫉妬を抱かないように一線を画して。
逃げ続けてきたものに、真正面から立ち向かうのは、怖い。
レイスは視線を、リオンの後ろのクラウンに戻す。 少年は、長い話に飽きたように宙を浮いている。
「お話、もう終わった?」
そして、また左手が青く光りだす――
「リオン、危ない!」
彼女は振り返り、攻撃を盾で防ぐ。 水流は盾で拡散し、あたりに水しぶきが飛んだ。
「攻撃は私が守るから。今度は……私が守るから。レイスが私達のこと、守ろうとしてくれたの、分かってるから」
彼女はこちらを振り返る。その顔は、笑顔だった。
彼女の持ち前の笑顔を、普段と変わらない笑顔を、こちらに向けている。
レイスには分からなかった。
あんなに酷いことを言って、リオンたちを突き放したのに。 過去に何人も、いくつもの町や村を破壊したのに。 どうして自分を守ってくれるのか。
理由は分からない。しかし、彼女が自分を信頼してくれている事は事実だ。
その信頼には、応えたいと思った。自分のことを信じて、守ろうとしてくれる彼女のを事を、見過ごすなんて出来ない。
……出来るだろうか。自分と向き合うという、十年がかりでも出来なかったことを、今、出来るだろうか。
レイスは立ち上がる。
そして、クラウンの方へ歩み寄る。今度は身を呈した自己犠牲のためではなく、戦うために。 一歩、また一歩と距離が縮まっていく。
幼い自分は、不可解な顔でこちらを見てくる。 無理もない。ずっと、過去の自分を突き放して逃げてきたのだから。
「こうして向き合ったこと、いままでありませんでしたね」
「……何、言ってるんだ……」
幼い自分は、小さい。背丈は140センチくらいだろう。今の自分と30センチ以上も違うのか。頭一つ分以上違うではないか。
純粋無垢な瞳。嫉妬と自己顕示以外、何の色にも染まっていなかった幼い瞳を、レイスは見つめる。
「あのときの私は、強かったですね」
今の自分は、弱い。体を得たせいで、病気と怪我の脅威にさらされるようになった。それに、寿命という避けようのないことにも。 小さいときの自分と相対しているだけなのに、こんなにも自分の心は震え上がってしまっている。
しかし、体を得て、道徳を得て、心を得たおかげで……今の自分にはできることがある。
レイスはおもむろに左手を伸ばす。 指先はかすかに震えている。彼は深呼吸して、心を落ち着かせる。 そして、微笑む。他者に向ける優しさを、今度は自分にも向けなければ。
レイスは、幼い自分の頬へ、そっと触れた。
貫通はしない。レイスの指には、そして過去の自分の頬には、たしかに肌のぬくもりが伝わった。
「ずっと……こうしてあげられませんでしたね」
幼い自分は、人を殺す中で何を欲していたのか。それは自分自身が一番良く知っていた。 誰かの温もりが欲しかった。たったそれだけのことだったのに。
クラウンは、幼い自分は、頬を撫でられながら静かに涙をこぼす。
「さわれる……」
涙の一滴が頬を伝い、零れ落ちたとき。
クラウンと周りの景色は、静かに透けて消えた。
Ⅱ- 3
景色が明転し、まぶしさに二人は目をつぶる。
瞼の裏から伝わる光が弱くなったのを確認し、目を開くと、そこは元の廃村だった。
「戻ってきたんだ」
リオンがいう。
レイスも頷く。過去の自分と向き合えたから、クラウンの変化は解けたのだろう。 リオンの助けがあったこそ。自分はリオンに守られたのだ。
彼女の方をみると、満面の笑みを浮かべていた。さっき泣き崩れていた顔は、どこへいったのか。 レイスが驚いていると、リオンはバッと抱きついてきた。
「やった! やったよレイス! 昔の自分に勝ったんだよ!」
血がつくことも厭わずに、リオンはレイスに抱きついてぴょんぴょん跳ねる。
「リ、リオン落ち着いて」
クラウンは、変化を解かれただけだ。まだ倒したわけではない。
「クラウンが何に変化したのか分からない今、あれを探さないと」
「あ、そっか」
リオンはそう言って、足元の剣を拾おうと地面を見る。
そこには、かさかさと動く一匹のクモがいた。 体長5センチほど。リオンは思わず飛びのき、悲鳴を上げる。
「いやあ、ク、クモ!!」
「え、リオン蜘蛛が駄目なんですか?」
彼女はレイスの胸の中で頷く。
「むかし友達が悪ふざけして、服の中に入れられたことがあって……正直、今は火事よりこっちのがトラウマ」
レイスは苦笑する。 男友達の悪戯に巻き込まれたのだろう。女の子らしいトラウマだ。
クラウンが変化したものは、この蜘蛛と断定していいのだろう。
「それじゃあ、一緒にこの魔物を倒しますか」
レイスは足元の剣を拾い、鞘から抜く。
リオンはレイスから離れて、杖を構えなおした。
石突の部分が蜘蛛に刺さるように杖を持ち、顔をそむけつつ狙いを定める。
「いきますよ。一,二の……」
三。
二人の剣と杖は同時に蜘蛛を貫く。
そして、魔物との壮絶な戦いはようやく幕をおろした。
*
「顔を上げなさい」
ライラの声が、頭上から聞こえる。
「あげられません」
レイスは腰から頭を下げた姿勢から動くつもりはなかった。
ライラは、自分が殺した人間の遺族に当たるのだ。いまさら事実を隠し、保身するつもりはない。 それに、クラウンとの戦いの前に放った言葉がライラを深く傷つけたことも、十分理解していたつもりだった。
ライラの声が聞こえる。
「あんたにはまだ話してもらいたいことがあるの。どうして人を殺すようになったの? 経緯と理由をきかせて。頭を上げろといったのは話をさせるためよ」
レイスは少し躊躇したが、仕方なく頭をゆっくりとあげる。今の自分には、ライラが納得いくまで全て話す義務がある。 傍らにいるリオンにも、自分の出生を聞いてほしかった。
レイスは、人を殺すようになった経緯を話した。
そして、体のない”ゴースト”の状態だった自分が、なぜ今は普通の人間と同じように生きているのかも。
*
十年前。
まだレイスに体がなく、殺人を繰り返していた頃。
ライラの故郷となった町で、彼は殺人を繰り返していた。残りの人間は八人。あと七人殺して、次の町を探しにいくつもりでいた。
とある女性に、声を掛けられるまでは。
「もう、やめて」
自分の背後で、声がした。
若い女性の声。透き通った、繊細な声だった。
振り返る。そこには、十五歳くらいの少女が立っていた。 空色の髪、空色の目。服も淡い空色。
彼は驚愕した。少女の瞳はまっすぐに、他でもない自分の瞳を見つめていたから。
目が合う。
それすら、彼は初めて経験した。
戸惑う彼をよそに、彼女は続ける。
「お願い。もう人を傷つけるのはやめて」
その言葉は、まっすぐ自分に向かって放たれていた。
彼は、久々に発する言葉を、その少女に投げかける。
「……見えるの?」
彼女は、頷いた。
会話。
初めての会話に、彼は緊張する。そして疑問にも思った。
「どうして、見えるの?」
「私も、きみと同じだから」
「同じ?」
「きみは、魔法で作られたんだよね。魂だけ」
少女の問いに、素直に頷く。
「私も、そうなの。魔法で作られた人間。私は体もあるのよ」
そういうと、少女はこちらに手を差し伸べる。
――僕に、触ろうというの?
緊張するなか、指が近づく。体に触れる、と思った瞬間、彼女の指は体を通り抜けた。
「……やっぱり」
彼女は悲しげに、そういった。
何者なんだろう、彼女は。 殺人鬼の自分に対し、まるで普通の男の子とのように接する。
「君は何がしたいの?僕を止めたいの?」
「ううん。私には分かるよ。君は、他の人と同じように体が欲しいんだよね」
いきなり核心を突かれ、彼は戸惑う。
体があれば。他の人に見える体があれば。声があれば。手があれば。
こんなこと、しなくてもすむんだ。
彼は、頷く。そして、言う。
「欲しい。僕も、みんなと同じようになりたい」
空色の少女は、ふっと微笑んで、そして言った。
「いいよ。体、作ってあげる」
Ⅱ- 4
半日後。少年と少女は、町外れの小屋にいた。そこは少女の家だ。
居間のイスに腰掛け、少女は語った。
「私、魔導師の研究施設で生み出された人間なの。 魔力で人間を作ることに成功したあの人たち達は喜んだわ。そして、しばらくの間私のことを本当に大切に育ててくれた」
彼は少女の話に口をはさむことなく、静かに聴いた。
少女は続ける。
「数年の間、私は研究施設から一歩も出ずに育ってきた。でも、そんな生活嫌になったの。 だから、私は逃げ出した。研究資料を全部持ち出して、今後私と同じものが作り出されないように」
その資料がこれ、と、少女は後ろの棚を差す。中には分厚い魔道書の数々。羊皮紙の束も見える。
「この資料の中には、体だけ生成する方法も書いてある。これで、あなたは人間になれるわ」
人間になれる。その言葉に、彼は揺れた。
あれほど嫉妬し、羨望した体が手に入る。
「どうする?」
少女の問いに、首を横に振る理由は無かった。
*
まばゆい光に包まれたあと、彼は目を開く。
両足をしっかりと地に着け、自分の足で立つ自分の姿。
一見すると、あまり変わったようには思えない。本当に、体が出来たのだろうか?
少女が、微笑んでこちらへやってくる。そして、手を差し伸べた。
「さあ、触ってみて」
彼も、手を出す。ゆっくりと、慎重に。
もしまた少女の手をすり抜けてしまったら。唯一の望みが、すりぬけて零れ落ちてしまったら。
そう思うと、怖い。
しかし、手をとらないと、自分はずっと、永遠にこのままだ。
それは嫌だ。
彼は手を差しのばす。
そして――
手は、少女の指先に触れた。
柔らかい指先だった。彼は手をおもむろに滑らし、指から手のひらを触っていく。 手を握ると、包み込まれるようなぬくもりが伝わってきた。
「さわれる……」
少女は頷く。
「うん、さわれるんだよ」
彼は、うなずいた。何度も何度も、うなずいた。
いつの間にかこぼれていた涙を、少女は優しく拭った。
*
彼が少女のことを「義姉さん」と呼ぶようになるまでに時間はかからなかった。 彼は、外見上十歳くらいに見えた。少女は十六歳。ちょうど姉弟のようだ。
義姉はある男性を紹介してくれた。三十近い男。鎧を身にまとい、剣を提げたその格好は、男が騎士であることを示していた。
義姉はいう。彼は、自分にとって父親に近い存在なんだと。今の自分がいて、この生活があるのは彼のおかげだと。
だから、君もこの人のこと、お父さんって呼んで良いんだよ。 義姉が笑ってそういうと、男は少し照れくさそうな顔をした。
男――いや、養父は言う。
「息子なんだし、名前をつけないとな。呼ぶ名前が無いんじゃ可愛そうだ」
「名前、かぁ」
自分に名前がつく。魔法で作られた男の子から、普通の人間としての名前が。
養父の横で、義姉は辞典を取り出しペラペラとめくりだした。
「人の名前って付けるの初めてだからなあ。犬とかネコはあるんだけど……」
犬やネコにつけるような名前は、いくらなんでも勘弁だ。
彼は、義姉に辞典を貸してもらうよう頼んだ。そして、辞典のとある言葉を引く。
ページを見つけた。 そして、目当ての言葉を見つけた。
「僕、この名前がいい」
引いた言葉は”生霊”。
生まれながらにしてゴーストと変わりない存在を余儀なくされた彼。 そして、その結果握りつぶしてしまった多くの命。
それを忘れないために、自分自身で戒めるために、彼自身が選んだのは。
生霊を指す、”レイス”という言葉だった。
レイスが養父から剣術を習い、国軍として人の命を守る仕事に就いたのは、その数ヵ月後である。
*
レイスは、ライラとリオンの目の前で、全てを話し終えた。
しばらくの間、二人の女性は絶句したまま何も話さなかった。
無理もないだろう、とレイスは思った。
信じてはもらえないかもしれない。それに、殺人を正当化する理由も何も無いのだから。 自分のために人を殺し続けた。その事実は、何をしても変わりようの無いのだから。
やがて、ライラが口を開いた。
「……呆れたわ」
「ライラさん」
「そんな理由で、あたしの家族や友人を殺したって言うの?まるっきり自分の欲求のためじゃない」
ライラの言葉に間違いは何一つ無い。今自分が国軍に入って剣を振っているのも、自分を償うためだ。
「一つ聞かせて」
「はい」
「あんた、体を作ってもらってから……自分のためだけに人を殺した?」
レイスは返答にためらう。
国軍に入ったのは自分のためだ。しかし、その戦闘で敵兵を殺すのは、自軍や国民を守るため、ともいえる。 戦争の渦中で、殺人の絶対的な理由を求めるのは果てしなく困難なことに思えた。
「分かりません。ただ……昔のように、嫉妬心や顕示欲を示すための殺人は、してません」
「なら、それでいいわ」
ライラはそういうと、廃村の門へ戻ろうとする。
「ライラさん、どこに?」
「決まってるでしょ。魔物討伐は終わったの。帰るわよ」
ライラは何も言わず、歩いていく。
許された、のだろうか。
”なら、それでいい”の意図が、レイスは完全には理解できなかった。
「ライラさん」
彼女を呼び止める。
「何よ」
「……」
なんて言葉をかけて、確認すればよいのか分からない。
言葉に詰まるレイスに、ライラは声をかける。
「言っとくけど、許したわけじゃないわよ。だけどアンタの態度と向上心に賭けるわ」
「向上心?」
「もう一度自分のために人を傷つけたら、本当に殺しにいくから。これでこの話は終わりよ」
レイスは、そのセリフに黙って着いていくしかなかった。
*
帰路につく中、ライラの後ろで歩くレイスに、リオンが追いつく。
横に並ぶリオン。レイスも彼女も何も言わず、数分歩く。
しばらくためらったあと、リオンがレイスに話しかけた。
「レイス」
「何ですか?」
「レイスは……まだ、昔の自分が許せない?」
彼はしばし考え、いった。
「そうですね。恐怖心はなくなりましたが……今でも自分自身は許せませんし、許してはいけない存在だと思っています」
少し間をおいてから、彼は続けた。
「でも、こうして自分のことを分かってくれる人が隣にいますから……怖くはありません」
えっ、という声を漏らし、リオンがこちらを見上げる。
頬が少し赤い。
「レイス……」
「頬が赤いですよ?」
赤い頬は更に赤みをまし、うろたえる。
「ち、ちがうもん!これは――」
彼女の挙動に、レイスは笑みをこぼした。
三名の討伐隊は、帰路につく。
数日間空を覆っていた雲の合間から、わずかに陽光がさしかけていた。
エピローグ
グレン元帥は、自室内でレイスの作成した報告書に目を通していた。
そしてレイスは、元帥が眉一つ動かさずに淡々とした表情で報告書を読むのを、目の前で見守るしか出来なかった。
報告書の内容は勿論、クラウンとの戦闘だ。 自分の経歴なしでは報告書が書けず、かと言ってライラとリオンがいる手前嘘も書けず、結局事実をありのまま記載した。
養父と義姉以外には、十年間ずっと隠し通してきた秘密。自分が人間ではないという、他人との根本的な差異。 それを、限りなく静寂な形で、レイスは上官に打ち明けているのだ。
報告書をまとめるのにも、ずいぶんと時間がかかった。 何度も書き直しをし、推敲を重ね、出来るなら自分の経歴を曖昧にぼかして書けないか悩んだ。 しかしそう思うたび、ライラのあの悲痛な表情が頭に浮かぶ。
もう自分は逃げてはいけない。
立ち向かわなくてはいけない。
そう思い、ありのままの事実を報告書に書き起こした。
読み終わったグレンが、表情を変えぬままレイスに訊く。
「……おまえ、これ本当の話か?」
「すべて事実です」
「よくオレ達にいままで隠し通してたな」
「本当はずっと隠すつもりでしたが……」
元帥は、何て顔をするだろう。 そう思うと、レイスはグレンの顔をまっすぐ見ることが出来なくなった。 視線を横にそらす。
すると、
「そういえば、俺とお前が始めて会った日覚えてるか?」
優しい語り口でグレンは言う。 その口調を聞き、レイスは視線を戻した。元帥の表情はいつもと変わらない笑顔だ。
「お前あの日さあ、北東門の番兵みんな倒して『とりあえず倒してみたんですけど』とか言ってたよな」
入隊した日のことを、レイスは思い出す。そういえば、そうだった。 軍に入りたい、と門番に伝えたら、見た目で十四歳以下だと分かってしまったらしく、門番に笑い飛ばされた記憶がある。 今思えば無謀だった。入隊可能の年齢すら知らずに、よく身一つでのりこんだものだ。
「お前は知らなかったと思うけどよ、あの日お前が相手したのは曹長一人、伍長四人、少尉一人だ。よく相手できたな」
「……噂には聞いてましたが、本当に記憶力がいいのですね。普通は人数と階級まで覚えてませんよ」
グレンは豪快に笑う。本当に、いつもの元帥だ。 自分の経歴を知った上で、この人は、ちゃんと自分のことを『部下』としてみてくれている。
「レイス、お前最初から剣を使う兵科を志願してたよな。あれは、魔法で人を殺したくなかったからか?」
レイスは頷く。
養父は北の大陸の騎士で、剣を使っていた。その養父に憧れていたという理由もあったが、大きな理由は元帥の言ったとおりだ。 養父や義姉のように、自分の力を使って今度は何かを守れる存在になりたかった。 考えた末、手に取ったのは剣。
武器の重さが、人を切るときの感触が、しっかりと自分の腕に残るように。
魔法を使って人を殺める存在ではなく、武器を使って人を守る存在になれるように。
魔法のコントロールの方法も、義姉から教わった。そして、魔法が剣戟の補助となるような戦い方を見出した。 もう、人をいたずらに殺すような魔法の使い方はしない。剣を提げてアルファルド城へ向かった十年前のあの日、固く自分に誓った。
「もう一つ訊いていいか」
グレンは続ける。
「リオンの嬢ちゃんの話をすぐ信じたのは?」
「あれは……なんとなく、リオンと自分が重なって見えたような気がして」
リオンと始めて会った、あの日。 戦場に一人きりでいた少女。その姿が、体を持たない時期の自分と重なって見えた。 世界に一人だけたたずんでいた自分に、手を差し伸べてくれたのは義姉だった。 リオンの姿を見て、話を聞いて、今度は自分が義姉のような存在になる時だ。そう思ったのだ。
その時、レイスの後ろのドアからノックの音がした。返事も待たずにドアを開けたのは、リオンだった。
「レイス、やっぱりここにいた! あのね、傷の手当をするから処置室に来てほしいんだって」
「傷?」
「そう!この間の闘いの傷、まだ治りきってないんでしょ?ダメだよ無理しちゃ!」
レイスが応える間もなく、リオンは彼の腕を引っ張る。
「そういうわけでグレン元帥、レイス借ります!」
「おー、返さなくていーぞー!」
リオンは笑って礼を告げると、レイスをさらってドアを閉めた。
部屋にはグレン一人だけが残る。彼は、椅子の背に深くもたれかかった。 そのとき、左肘がインクのビンにぶつかり、中のインクを豪快にこぼしてしまった。
報告書も半分以上が黒く染まった。 報告書は各師団の元帥が承認した後、魔物の発生動向の資料として製本する。 書き直しは必須だろう。勿論レイスの経歴も。 グレンはしばらくインクにぬれた報告書を眺め、そしてニヤリと微笑した。
「おっと。さて、元の文章はなんだったか全然思い出せねえな。まあ適当にごまかしとくか」
End