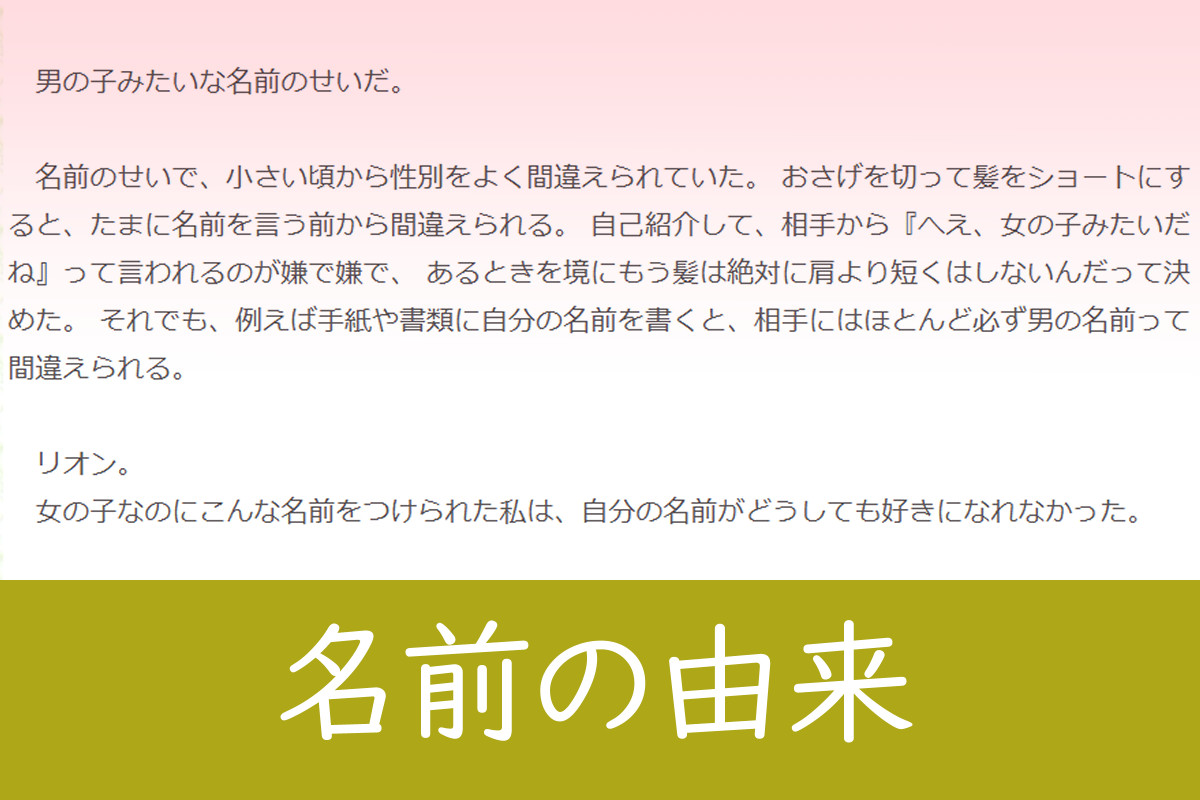Ⅰ
男の子みたいな名前のせいだ。
名前のせいで、小さい頃から性別をよく間違えられていた。 おさげを切って髪をショートにすると、たまに名前を言う前から間違えられる。 自己紹介して、相手から『へえ、女の子みたいだね』って言われるのが嫌で嫌で、 あるときを境にもう髪は絶対に肩より短くはしないんだって決めた。 それでも、例えば手紙や書類に自分の名前を書くと、相手にはほとんど必ず男の名前って間違えられる。
リオン。
女の子なのにこんな名前をつけられた私は、自分の名前がどうしても好きになれなかった。
*
春。寒さがふっと和らいで、空気や花がほころぶ、4月。11歳の誕生日を迎えたその日、私は何気なくお母さんにきいた。
「ねえ、私の名前の由来って、なに?」
ケーキの生地を混ぜているお母さんの手が、ふと止まった。 ちなみに、お母さんのケーキ作りは『焼く』ときに2回失敗しているからこれで3度目。 『今日はリオンの誕生日なんだから、私が作るわ!』って意気込んでたのに案の定。 ホントに、料理を焦がすのだけは誰よりもうまいんだから。
「どうしたの、急に」
お母さんは生地を混ぜる姿勢のまま、私のほうを見て言った。
「うーん、なんとなく気になって。今日誕生日だし、聞いてみようかなって思っただけ」
「……そう」
お母さんは、視線を伏せて黙ってしまった。それきり、あんなにせかせかと動かしてた手がぴたりとやんだ。
どうしたの、急に? 私のほうこそ、聞きたくなる。 さっきまであんなに楽しそうにケーキ作ってたのに。 生地が炭みたいになっても、『大丈夫、もう一度作り直せばいいのよ。お母さん負けない!』って言ってたのに。
両手に抱えた調理器具を静かにテーブルの上に置いて、お母さんは私の方に向き直った。 そのうえ、エプロンまではずし始めた。 なに、どうしたの?
「……リオンには、まだこの話、してなかったわよね」
視線を伏せたまま、話し始める。 まさか私の名前、深いワケがあってつけたのかな。聞いちゃいけないような理由でもあるの?
実の母親と話すのに、なんだか身構えてしまう。私はイスの背もたれに預けていた背中を、しっかりと起こした。
「リオンの名前はね、」
お母さんが、話し始める。
「リオンの名前は、お兄ちゃんがつけたのよ」
Ⅱ
「お兄ちゃんが? お母さんでも、パパでもなくて?」
お母さんはうなずく。
お兄ちゃん。
私より二つ年上で、パパゆずりの黒髪のお兄ちゃん。
……私が5歳のときの火事で、パパと一緒に死んじゃった、お兄ちゃん。
正直に言うと、その頃の記憶はほとんど無い。 外で遊んでばかりいた私と正反対に、家でよく本を読んでいたイメージが強く残っている。 でも、時々パパと一緒に外で遊んでいたような。 顔も、髪型も、声もおぼろげにしか覚えてないけれど、それでも大切な私の家族。
お母さんは、話す。
「お兄ちゃんはね、実は双子で生まれてきたの」
「えっ」
私は驚いて声を上げた。
双子?そんな話、いままで一度も聞いたこと無かった。 双子って事は、もう片方のお兄ちゃん(お姉ちゃん?)はいったいどうしたんだろう。
「お兄ちゃんたちが生まれてきたときは、お母さんね、それはビックリしたのよ。 お腹もあまり大きくならなかったし、まさか双子だなんて思わなかったの。 でも、それもそのはずだったのよ」
お母さんは一息おいた。口元は微笑んでいるのに、とてもさびしそうな悲しそうな眼をして。
「片方の子供はね、片方は……すごくすごく小っちゃくて、手のひらくらいの大きさしかなかった。 生まれたときには、心臓はもう……動いてなかったの」
「それでもね。それでも、小さいほうの子供も男の子だっていうことが分かって……。眼も、口も、鼻も、指だってちゃんとあるのよ。 今だから言えるけど、辛かった。とてもとても辛くて、パパの前で自分を責めたのよ。あの子達を悲しい目に遭わせたのは自分だって」
なにも言えなかった。なんて言えばいいのか、分からなかった。
生まれてきた赤ちゃんがもう死んでいる。母親としてできることを、してあげられなかった。 お母さんのそのときの苦しみは、私にもちょっとだけ分かったから。
お母さんは、少し赤くなった目頭を触って、話を続ける。
「元気に生まれてきてくれたお兄ちゃんの方は、生まれてからも、とても元気に育ってくれた。 私のかわりにパパが面倒を見てくれることもあって……。子育てで辛いことも沢山あったけど、それでもなんとかあの子を育てられた。
そして、リオン。あなたがお腹の中にいることが、一年と少し経って分かったのよ」
Ⅲ
お母さんが、優しく私に笑いかけてくれる。その表情を見て、私もなんとなくほっとした。
「リオンとお兄ちゃんは2つ差があるから……あなたがお腹の中にいるときは、お兄ちゃんは丁度2歳になったばかりね。 最初はね、子供の名前は生まれてから決めようって思ってたの。性別も分からなかったし。
でも、ある日大きくなった私のお腹を見て、お兄ちゃんが呼んだのよ。
『りおん』って」
「……ホントに? はっきり、そう呼んだの?」
「もちろん。私のお腹を触って、2,3回くらいかなあ……『りおん』って呼んだのよ。パパと一緒に聞いたもの、間違いないわ」
お母さんはとてもうれしそうな顔をして、そういった。
ホントに、本当にお兄ちゃんが「リオン」って呼んだんだ。 まだ2歳なのに。
「それでね、お母さん、思ったの」
お母さんのうれしそうな顔に、涙のあとがついているのを私は見つけた。
「ああ、このお腹の中の子供は……きっと、あのとき死んじゃったおにいちゃんの、片割れなんだって」
お母さんの声が、かすかに震えた。
「お兄ちゃんがさびしくないように、ちょっと遅くなっちゃったけど……」
声が震えて、曇る。 さっきよりも真っ赤になった目頭に、涙をいっぱいためて、それでもお母さんは続ける。
「もう一度……もう一度、会いに来てくれたんだなあって……。 お兄ちゃんはきっと、それを無意識に感じて『リオン』って呼んだんじゃないかって、思ったのよ。 きっと、お兄ちゃんは私のお腹の中にいたときから、双子のきょうだいに名前をつけてたのね」
「……」
「だから、生まれてくるこの子には『リオン』ってつけようって決めたの。女の子だから、性別に合わない名前になっちゃったけど。 ごめんね」
大きく首を横に振った。
いいんだ、もう。謝らなくていいんだ。
もう充分だから。 お母さんが私を生むまでに辛い思いを沢山したの、もう充分わかったから。
だから、もうそれ以上話を続けようとしないで。
じゃなかったら、私、もう目に溜まってる涙がこぼれそうだよ。
なのに、お母さんは続けた。
「お兄ちゃんは、あなたが生まれてくるのをとても楽しみにしてたの。でも……たった5年しか、一緒にいさせてあげられなかった」
お母さんのため息がかすかに聞こえる。もう、にじんだ視界しか見えないから、私は下を向いた。
「あの子を……私は、母親として十分に愛してあげられなかったから。あの子をつらい目にあわせた、駄目な母親だから「そんなことない!」
大きな声で、私は遮った。
「駄目な母親なんていわないでよ。だって、だってお母さんは」
声が震える。うまく声が出せない……いやだ、本当に泣きそう。
「私のことちゃんと育ててくれたじゃん。こうして、私が11歳になるまでずっと。 誕生日だって、ケーキ作ってお祝いしてくれて、生地焦がしてもなんども作り直してくれて」
視界がゆらいで、頬を何かが伝った。 わたし、泣いてる。
「駄目なんかじゃない、立派な私の、ううん、私たちのお母さんだよ」
お母さんの表情が崩れて、まるで子供みたいにポロポロ涙をこぼした。私たちは、それからちょっとの間だけ二人で泣いた。
忘れられない、11歳の誕生日。
お兄ちゃんたちがつけてくれた、男の子っぽいけど大切な名前。
お兄ちゃん、名前キライなんて思ってごめんね。
大切にするから、この名前。
End