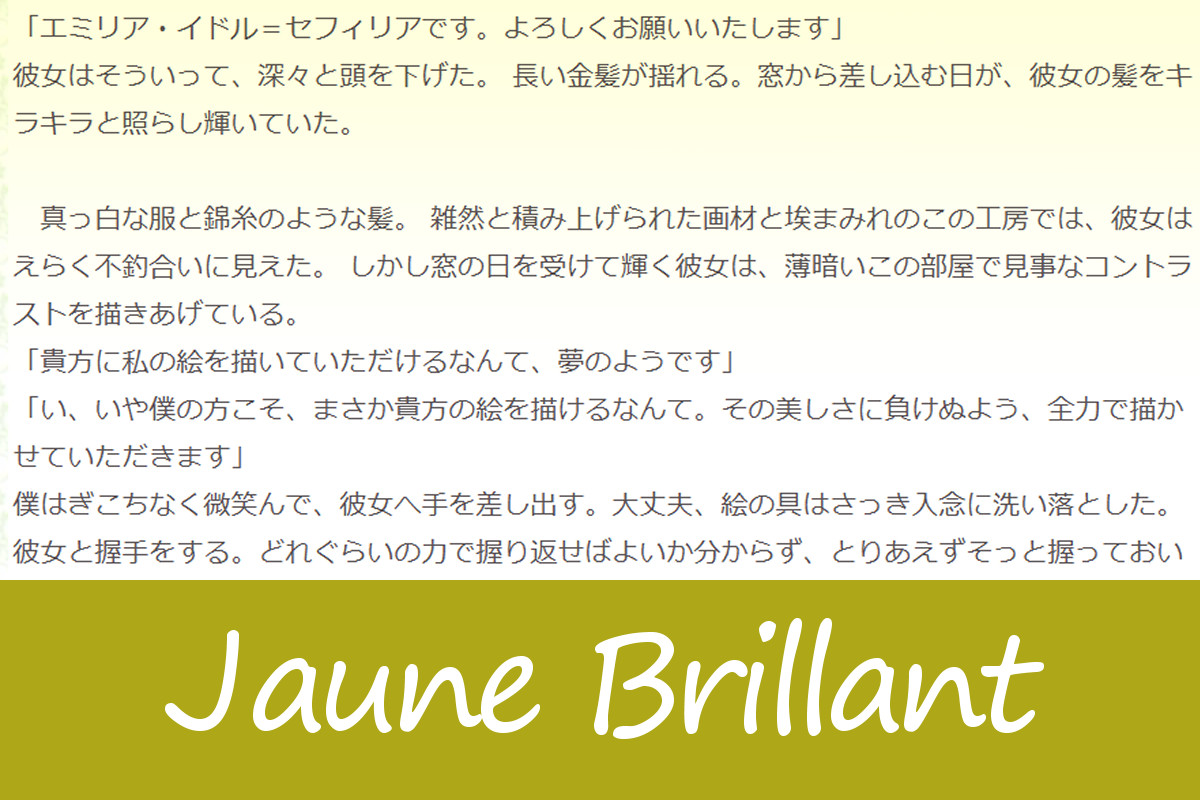Ⅰ-1
「マクベインさん、ですね」
僕が工房の戸を開けたと同時、初老の男はそう言った。 穏やかな眼差し。ところどころに白が交じっている、髪と髭。 白と赤にを基調としたローブは、男が教会の人間であることを示している。
「そうですが」
いささか冷たく返事する僕とは対照的に、初老の聖職者はにこやかに微笑んだ。
「唐突にお邪魔して申し訳ありません。私はピエトロ。司祭を務めております。 画家のあなたに、是非とも――」
「お仕事なら、お受けしませんよ」
彼の言葉を待たずに、僕は依頼をつっぱねた。 この時期に、この街外れの小さな工房にわざわざ教会の人間が来る。 その意図は、僕でも大体予想できた。
この街に、小さな聖堂が新しく建てられる。 すでに建設は殆ど完了していて、あとは内装を完成させるだけなのだとか。 友人から聞いた話によれば、なんでも天井に大規模なフレスコ画を描いているらしい。 町中の画家が今に駆り出されるぞ、と彼は話していたが。その依頼がとうとう僕にまで来たらしい。
フレスコ画は専門じゃない。それに、聖堂の建設に携わるなんて僕は二度とごめんだった。 ……独立前は、よく聖堂のフレスコ画を描くことがあった。が、良い思い出なんて一つもない。
「聖堂のフレスコ画のお話でしょう? 僕はそちらの専門ではないので」
「いえ、貴方に描いていただきたいのはフレスコ画ではないのです」
「それでも依頼は受けかねます」
「……何故」
ピエトロと名乗る司祭は、顔色を変えずに訊いた。穏やかな眼差しと口元は微動だにしない。 それがかえって言いようのない威圧感を与える。しかし、僕も負けてはいない。
「絵の種類に関わらず、僕は宗教画は描かないので。父の工房から独立するとき、そう決めました」
僕は続けた。
「ですから、お引取り願えますか」
司祭はしばらく沈黙したあと、口元に手を当て考え込んだ。
「マクベインさん、どうしても、お引き受けは出来ませんか」
「はい」
即答する。この信条だけは、どうしても曲げるわけにはいかない。
司祭は尚も考え込む。依頼は受けないといっているのに、何故早く帰らないのか。 数十秒ほどたっぷり考えた司祭は、ぱっとひらめいた様に顔をあげた。
「では、これはどうでしょう。貴方には、あるお方の”肖像画”を描いていただきたいのです。宗教画ではありません」
「……肖像画といっておきながら、どうせ大司教か誰かの絵を描かせるつもりでしょう」
以前、似たような類の依頼をされたことがある。その時も当然、お断りをした。しかし、この男は続ける。
「いいえ、司教ではありません。彼女は聖職者であって聖職者ではない」
聖職者であって、聖職者ではない?
「誰なんです、その人は?」
話に食いついた僕を、司祭の眼差しは見逃さなかった。
*
「エミリア・イドル=セフィリアです。よろしくお願いいたします」
彼女はそういって、深々と頭を下げた。 長い金髪が揺れる。窓から差し込む日が、彼女の髪をキラキラと照らし輝いていた。
真っ白な服と錦糸のような髪。 雑然と積み上げられた画材と埃まみれのこの工房では、彼女はえらく不釣合いに見えた。 しかし窓の日を受けて輝く彼女は、薄暗いこの部屋で見事なコントラストを描きあげている。
「貴方に私の絵を描いていただけるなんて、夢のようです」
「い、いや僕の方こそ、まさか貴方の絵を描けるなんて。その美しさに負けぬよう、全力で描かせていただきます」
僕はぎこちなく微笑んで、彼女へ手を差し出す。大丈夫、絵の具はさっき入念に洗い落とした。 彼女と握手をする。どれぐらいの力で握り返せばよいか分からず、とりあえずそっと握っておいた。
駄目だ、緊張している。心臓に毛の生えたような父親とは違い、僕は緊張しやすいんだ。 こんな調子で、絵筆が握れるのか?
別に、僕は女性が苦手というわけではない。女性と付き合った事だって、何回かある。 僕が緊張しているのは、他でもない、彼女の地位のせいだ。
彼女の特殊な地位は、この国に伝わる神話に所以がある。
昔、二つの世界の『扉』を閉ざしてこの世界を創ったといわれる女神、セフィリア。 その血を引くものは金の瞳を持って生まれ、『扉』を守るための守護者となる。
それは一般の教養を得ている人なら誰でも知っている神話だ。 その神話の中心に立ち、世界を守る象徴となる人間…… それが他でもない、このエミリア・イドル=セフィリアだ。 扉の守護者という、なんとも仰々しい通称を持った彼女。その瞳は、神話どおり鮮やかな金色をしている。
あの司祭、だましたな。僕は”ある女性の肖像画”としか聞いてないぞ。 彼女は大司教なんかより、ずっと上の地位の人間じゃないか!
その人が、今僕とにこやかに握手をしているなんて。半日前の僕に話したら、きっと鼻で笑われるな。
肖像画は一日では完成しない。 数日間は、同じ服・同じ髪型でカンバスの前に座ってもらうことになる。 ちなみにその数日間は、彼女が僕の工房まで来てくれることになっている。 もちろん、工房の外には司祭という名のボディーガードつきで。
どうか、どうか何も起こらないでくれ。 無事にこの絵が完成してくれることを願い、僕は絵筆を握った。
Ⅰ-2
最初に抱いていた不安は一体なんだったのだろうか。 予想よりもはるかに順調に、筆は進んでいた。
右手では絵筆を進めながら、口では沢山彼女と話をした。 趣味、仕事の内容、好きな色から昔飼っていた動物まで。
僕は肖像画を描くとき、なるべくその人と話をしながら人柄をつかむようにしている。 そちらの方が、その人の性格や雰囲気を反映した絵になるからだ。
彼女の柔和な笑顔と穏やかな声のせいか、段々と絵の表情は優しく温かみを帯びるようになってきた。 ……良い仕上がりになりそうだ、そう確信した。
*
製作に入って3日目。この日は久々に雨が降った。季節は春を迎えたばかりで、雨が降ると一気に冷え込む。 絵の具の下準備をしながら、暖炉に薪をくべていると戸口からノックが聞こえた。 ドアをあけると、そこにはずぶぬれの彼女と司祭が立っていた。
「ごめんなさい、遅くなってしまって」
頭を下げる彼女を、僕はあわてて止める。
「いえいえ、この雨ですから無理もないですよ」
机の上のタオルを咄嗟につかんで、彼女に渡す。司祭の分も必要だろう。奥の部屋から取ってこなければ。
「とりあえず、お二人とも暖炉の前へ」
「申し訳ございません」
司祭はそういうと、彼女と暖炉の前へ座った。
二人が髪と服を乾かす間、僕は手持ち無沙汰になってしまった。 髪と服がぬれた状態で、カンバスの向こう側に座らせるのはあまりにも酷だ。 しかし絵が描けないからといって、二人を追い返すわけにもいかない。
そうこうしている内に、時間は昼時へとさしかかろうとしていた。 どうしようか、と考えていると。
暖炉の方から腹の鳴る音が聞こえた。 どちらのものか、あえて追及は――
「……エミリア様」
司祭があきれた口調で隣の女性を見る。彼女は顔を真っ赤にして、しばらくすると。
「司祭様、どうしてそこでお言いになるんですの……」
「え?」
「マクベインさんには知られたくなかったのに」
そこまで言って、ようやく司祭も合点がいったらしい。
「あ、も、申し訳ございませんエミリア様」
そんな二人のやり取りを見て、思わず笑みがこぼれた。
「僕、なにか作りましょうか」
一人暮らしだから料理は手馴れている。1人分の昼食が3人分になったところで、大して変わらないだろう。
「いいえ、そんなお手数はお掛けしたくありません」
彼女は首をぶんぶん横に振る。さっきの羞恥心が残っているのか、心なしかリアクションが普段より大きい。 かわいらしい。 彼女は続ける。
「それに、料理なら私も作れます。貴方にこれ以上のご迷惑はお掛けできません」
「ちょっとお待ちください!」
突然、司祭が割り込んだ。その形相は必死だ。普段は穏やかな司祭が、珍しく表情を変えている。
「エミリア様、今あなた『料理なら作れる』と仰いましたね……?」
「え、ええ」
「なりません! あのような消し炭を料理と称しては!」
「ひ、酷いわ司祭様。私あのときは頑張って作りましたのに! ただちょっと火加減を間違えただけで」
「私とマクベイン殿の胃を壊してはなりませぬ」
なるほど。 たまに料理が出来ない女性を笑い話の種として聞くが、彼女もそうだったのか。 司祭が顔つきを変えてまで止めるほどの料理を拝見してみたい気はやまやまだ。 しかし、体調を崩しては折角の大仕事に差し支える。
「僕、作ってきますね。お好きな食べ物はありますか」
彼女は狼狽した顔で、僕と司祭を交互に見比べる。 司祭の顔は変わらず、厳格な表情だ。対して、今の僕はいったいどんな表情をしているのだか。
やがて、彼女の中で何かが折れたらしい。情けない、申し訳ないといいたげな顔をして、
「……お任せ、致します」
こうして、僕と司祭の胃袋の平和は守られた。
Ⅰ-3
料理は二人に好評だった。 食卓に、3人も集まって食事をするのなんて本当に久々だった。 絵を描いているときは彼女とばかり話していたが、ここでは僕は聞き役に回った。
「おいしいわ。こんな心のこもった料理を食べるの初めて」
と、純粋無垢な笑顔で食事をする彼女。喜んでもらえてよかった。 彼女たちが普段どんなものを食べてるか見当もつかなかったから、少し不安はあったが杞憂に終わったようだ。
「エミリア様もこれほどの料理の腕があれば」
と、こぼす司祭の横で彼女はまた赤面する。
「だってどなたも私に料理を教えてくださらないんですもの」
「あなたが10歳のときに教えましたとも」
司祭はやや不満げに言う。
「その時は厨房ごと焦がしてあわや大火事でしたが」
「私が10のときのお話なのでしょう? それから10年以上経っているのだし、ほら、今やれば出来るかも」
「やった結果、消し炭が練成されたのでしょうが。しかもそれは7日前の話です」
ここで沈黙。もはや、彼女は司祭に返せる言葉が見当たらないようだった。 むむむ、という声が今にも聞こえてきそうな不満顔を浮かべる。
会話を聞きながら、僕は内心では驚いていた。聖女という言葉がぴったりの女性が、こんなにも赤面して狼狽するなんて。
そうか。彼女だって人間、なのだ。扉を護るとか、女神の末裔だなんていわれているが、彼女だって人間なのだ。 高貴な職に身を置きながらも、僕のような一般人と同じように泣いて、笑って、失敗して、成長していくのだ。
肖像画の仕事を依頼され、彼女とはじめて会ったときの緊張感はもはや完全に無くなっていた。 彼女は一人の女性だ。こうして僕と同じ食卓で食事をとって、会話して、笑いあっている。
僕は微笑む。
「エミリアさん、料理は慣れですよ。練習したらきっと上手くなります」
「マクベインさん……。ありがとうございます、その言葉がずっと欲しかったんです」
今にも泣きそうだ。潤んだ金の瞳に、一瞬どきっとする。悟られないよう、僕は視線を料理へと逃がしつつ、言った。
「そういえば、綺麗ですね。その瞳」
違う。何を言っているんだ僕は。目をそらしたのに、瞳の色の話題をふってどうする。
「ああ、この色ですか? はじめてご覧になったでしょう」
「そ、そうですね、そういえば初めてです」
まだ顔を上げる自信はない。とりあえず食事を口に運んで誤魔化しながら、返事をした。
「この金の瞳は、セフィリア家に代々伝わる瞳なんです。セフィリアの血を引くものは、必ず金の瞳を持って生まれる」
知っているさ。というか、最低限の教養がある人ならば常識だ。 そして、金の瞳を持つ人間はセフィリア家以外存在しないことも知っている。
まだ顔をあげられない僕なんか無視して、彼女は続ける。
「私の祖母も、私の父も、この金の瞳を持っていました」
「エミリアさんの、お母様方は?」
「母はセフィリア家とはまったく関係のない出身です。青い瞳がとても綺麗でした」
”でした?” まさか。
「もう両親はいません。兄弟姉妹もいないので、この金の瞳は現在私だけなのです」
視界の隅で、彼女が目を伏せたのが見えた。 いたたまれなくなって、僕はようやく顔を上げた。
「……ご愁傷様です」
「ありがとう。でも、寂しくは無いです。こうして司祭様たちがいるから。本当に私のことを心配してくれているのですよ」
胃を痛めてまでね、と付け足して彼女は笑った。 早々に食べ終えていた彼女は、皿を厨房の方へ運びだす。
「あ、僕がやります!」
そういって、僕は彼女の背中を追う。 ふと、乾きかけの長い金髪が揺れ、彼女の背中が垣間見える。 その背は細く、どこと無くさびしげにみえた。
窓の外では、冷たい雨が降り続いていた。
Ⅰ-4
あれから、2日たった。 おとといの雨がまるで嘘だったかのように、日差しがさんさんと降り注ぐ。 外は暖かい。いや、むしろ暑いくらいだ。 大荷物を抱えているせいなのか、日ごろの運動不足で体力を余計に消耗しているだけなのか。
昼前のやや閑散とした街中。人はまばらで、それぞれがそれぞれの目的地へと歩く。 そして、僕もそうだった。目的地は、建設中の聖堂だ。
どうしても外せない仕事が出来てしまい、彼女は聖堂を離れられないらしい。 だから今日だけは聖堂まで来て作業を進めて欲しい、との事だった。 聖堂に行くくらいなら、その日の作業は無しにしていただきたい…… と思ってはいたが、彼女と司祭にそれを言えるはずも無かった。
聖堂に着いた。外観とはうって変わって、中は思ったより大きい。天井が高いからか。
聖堂というと、物音一つしない静まり返った空間をイメージさせる。が、建設作業中の聖堂ではそうも行かない。 建物に反響し、柔らかな物音が絶えず上から降りてくる。 見上げると、製作途中のフレスコ画に黙々と筆を入れる画家たちが遠くに見えた。
人数は8人。良く見えないが、何れも若い男のように見える。 見知った背格好の人物はいない。流石に知り合いの画家はここにはいないか。
エミリアさん達を待たせてはいけない。約束している部屋へ向かおうと足を出した、その時。 廊下の角から、よく知った顔の画家が現れた。
白髪交じりの髪。深い皺。鋭い目つき。いかつい肩。絵の具とマメだらけの両手。 相手も僕の姿を捉えて、はっと目を見開いた。僕たちは立ち止まる。
なんでだ。なんで、あいつがここに。カンバスを抱える手に、思わず力が入る。
お互いがお互いの姿を見て、硬直していた。すると、僕のはるか後ろから若い画家の声がした。
「あっ、マクベインさーん! そこに置いてある絵筆、取っていただけませんかー!?」
もちろん、呼ばれたのは僕ではない。目の前の男にだろう。
男は返事をしない。 ……と思ったら、彼はいきなり怒号を僕の後ろの画家へ飛ばした。
「うるせえ! 今取り込み中なんだ、自分の筆くらい自分で取れ!!」
相変わらずの迫力だ。 若い画家はそれに押されたのか、あとで取ります、なんていってそそくさと逃げた。 まあ、無理もない。
若い画家を追っ払うと、目の前の男は僕をキッとにらみつけた。久しぶりだ、この視線は。何度経験しても慣れない。 すくみ上がるような、威嚇の視線。背筋が硬直して、僕は微動だに出来ない。
「なんでてめえがここにいやがる? 宗教画は描かない、とか青臭いことほざいたのはお前だろうが」
「関係ないだろ、父さん」
父さん、なんて呼ぶのは不愉快だ。 だけど画家として独立する前は、こいつを”師匠”なんて呼んでいた時期もあった。
いま思うととても馬鹿馬鹿しい。 父親の工房にいた頃の僕と、今の僕は違う。 負けじと僕も目の前の男をにらみ返す。
「それより、やっぱり宗教画を飽きもせず描き続けているんだね。相変わらず普通の人物画は描けないのか?」
「碌な作品一つも完成させねえで、ベソかきながらうちの工房でてった奴に言われる筋合いはない」
「僕は完成させていたじゃないか!」
僕は声を張り上げた。
思い返すだけでも気分が悪くなる。
作品を描いては”構図が悪い”と指摘され、
書き直したら”色がよくない”と批評され、
やっとの思いで完成させたら”絵への愛情が足らん”と非難され。
燃やされた絵は、数え切れない。割られた彫刻だって、何十何百とあるだろう。 フレスコ画にいたっては、僕が書いた部分の漆喰をすべて剥がされた。さぞかし大変な労力だったろう。
そして、父は宗教画以外の題材を描くことを決して認めなかった。 風景画、静物画、一般の人間の肖像画。それらを描くことを、父は決して認めなかった。 もともと父は宗教画家として名の通った画家だからだ。子どもにも、自分と同じ道を辿らせたかったのだろう。
しかし、それは失敗に終わった。耐え切れなくなって、僕が父の工房を飛び出したからだ。 作品を否定するときの父の目つきは、忘れたことがない。 威嚇し、拒絶し、冷徹な視線。
僕はいま、それと対峙している。
「とりあえず、そこを通してくれないか。僕は別の仕事で来ているんだ、そこに立たれると邪魔なんだ」
父は何も言わない。やがて、視線を一瞬僕のカンバスへと見やったかと思うと、彼は突然ひったくった。
反動で、一緒に抱えていた画材が床に落ちて散らばる。 僕の両手は一瞬で空っぽになった。
「何するんだ!」
父は黙ったまま、カンバスにかけてあった布を取り払った。
「おい、やめろ!」
僕が止める間もないまま、絵は父の前に露になる。
カンバスの中のエミリアさんと、父の視線が合う。 しばらく父はそれを見つめた後、僕に絵を突きつけて返した。
「……さっさと行け」
「言われなくても、そうするさ」
床の絵筆を拾おうと、僕はかがむ。視界の隅に、白いローブの裾がうつり込んだ。
エミリアさんだった。 彼女は戦慄と驚きの混じった顔で、こちらを見ていた。 彼女の顔が、さっと青ざめる。それは僕も同じだった。
見られた。 見られてしまった。父親との確執を、エミリアさんに見せてしまった。
「エミリアさん」
冷静になれ。 自分に言い聞かせながら、声を絞り出す。
「申し訳ないです、こんなお見苦しいところ――そうだ、もう約束の時間でしたね、わざわざ迎えに」
「マクベインさん」
僕の言葉をとめた、エミリアさんの声は驚くほど冷静だった。
「今日はもう、お帰りになって」
「で、でも」
「いいから。 そんな様子では、絵筆は握れないでしょう」
ようやく、僕は気付いた。 僕の両手は、震えていたのだ。
「明日、そちらの工房へお伺いしますわ」
エミリアさんはそういい残すと、背を向けて去っていた。
やっと思いで立ち上がると、父はもういなかった。