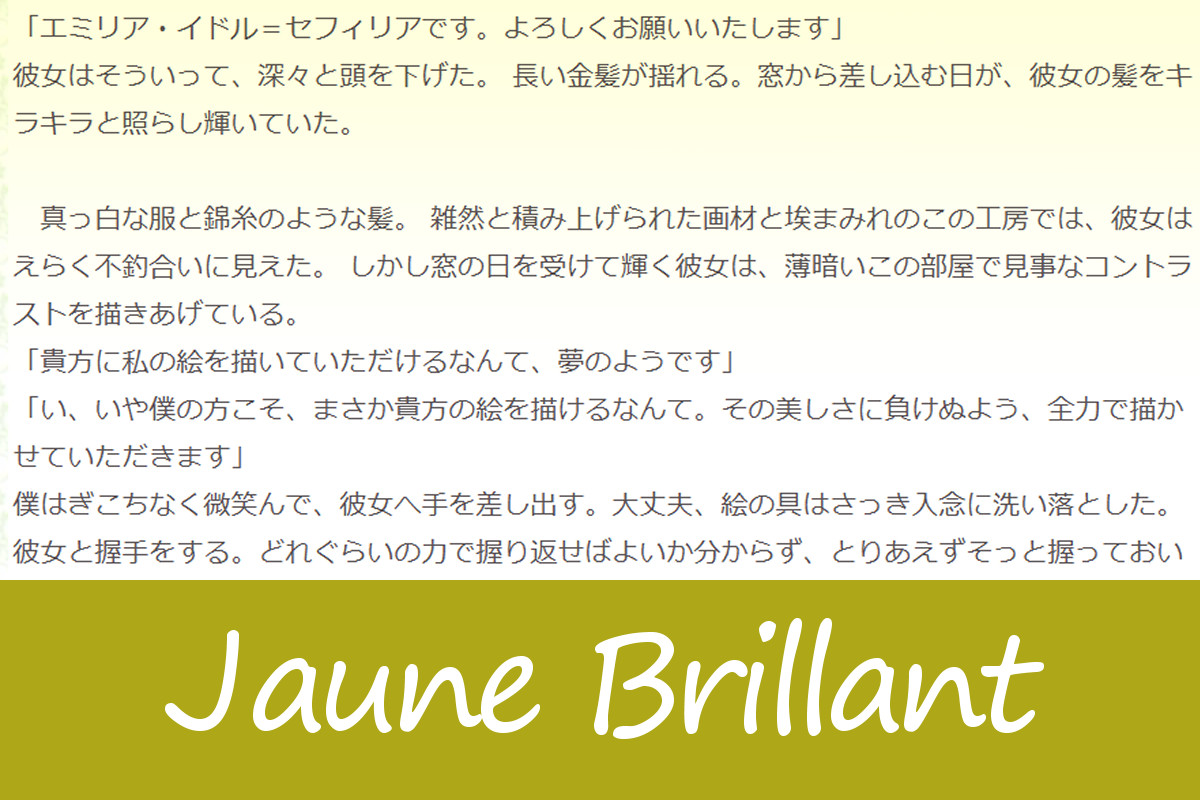Ⅱ-1
翌日。エミリアさんはいつもどおりの時間に僕の工房までやってきた。
「おはようございます。良いお天気ですね」
彼女はいつもと変わらず、穏やかな微笑を浮かべる。
「今日は私お手製の料理を作ってきましたの。お口に合うかどうかは分からないけれど」
そういって、彼女は包みを広げる。 なるほど、たしかにこれは消し炭だ。何の料理なのか、さっぱり分からない。 色は真っ黒、形はグズグズ、匂いがまったく無いのはいったいどういう原理なんだ。
そんな消し炭……もとい、料理から視線を彼女に戻す。 金の瞳と目が合った瞬間、僕は咄嗟に視線をそらした。あの雨の日のときとは別の理由だ。
彼女の目を見ると、思い出してしまうのだ。フレスコ画。大聖堂。父の視線。燃えて壊された僕の作品。
まるで心臓をつかまれたかのように、萎縮してしまう。
駄目だ。彼女相手に萎縮する必要なんてないのに。 それでも、心は言うことを聞いてくれない。
「……すみません」
僕は小声で言った。
女神の血を引くといわれる、金の瞳。僕はそれを見つめることが、できなかった。
*
それからというもの、彼女は毎日定刻ぴったりに僕の工房に訪れてくれた。 そして、いつまで経っても彼女と目を合わせない僕の様子を見ては、労いの言葉をかけて何もせず帰っていく。
「あなたが描けるようになる日を、ずっと待っていますから」
と。
自分が情けなかった。
勝手に親元をはなれ、勝手に独立した半人前ではあるが、それでも僕は画家だ。 自分の都合で絵筆が握れないなんて、賃金を貰っている身としてはありえない。
描ける、描けないではない。描かなくてはいけないのだ。 そんな義務感と、絵が描けない焦燥感に僕は刈られた。
そして、父との諍いがあってから丁度7日目のこと。 僕は聖堂へと足を運んでいた。
彼女は、今日もまた聖堂での仕事があり工房へは行けない。 だが、僕はカンバスに向かわない自分をどうしても許せなかった。 5分でもいい。彼女と向き合って、絵筆を握らなければ。 そうしないと、もう永遠に自分はこのまま進めない気がした。
聖堂の入り口を通ると、嫌でもあのフレスコ画が視界に映る。 今日も画家たちは天井に自らの絵筆で色を乗せている。 その中に、彼の姿もあった。
父は女神の髪の部分を担当している。黙々と、暗い金の絵の具で細く、長く、繊細に影を入れていく。 独特の絵筆の持ち方は、今でも変わらない。5本の指全部使って絵筆を握る。 傍から見るとまるで不必要な力を込めて描いているように見えるが、父の画風はどちらかというと繊細なほうだ。
下にいる僕どころか、隣の仲間を気にかける様子も無い。完全に集中している。 父は絵に視線を置いたまま、辺りを手で探っている。別の絵筆が欲しいのか? 左手が絵筆に当たる。と、筆は作業用に組んだ足場から半分飛び出した。今にも落ちそうだ。
父はあわてて、それを掴もうとして――バランスを崩す。
父の半身は宙に踊り出し、両足が足場から滑り落ちて……
彼は真っ逆さまに、僕の目の前へと落下した。
Ⅱ-2
「マクベインさん!」
呆然と絶句する僕の前で、若い画家たちが父へ駆け寄る。
父は動かない。
天井は高い。落ちたら、もし打ち所が悪かったら――
1人の画家が、父の上体を抱き起こす。 額から、血。
僕の頭は真っ白になっていた。悪い思考がぐるぐると回転を始める。
血だ。頭を打っている。父さんは。父さんはどうなるんだ。
その時だ。父が顔をしかめて、うなった。
「つ……」
「マクベインさん! しっかり!」
周りの者は、必死に父に呼びかけたり、肩を叩いている。 僕は何も出来ず、ただ唖然としてその光景を見ていた。
「うるせえ、黙って作業にもどれ」
ぐったりとはしているが、はっきりとそう言った。 意識はある。生きてる。
そう実感したとき、膝が折れて力が抜けた。 へなへなと座り込んだ僕に、父はようやく気がついたらしい。
「お前、また来たのか。帰れっつったろ」
「……天井から落ちても、減らず口は変わらないんだな」
このやり取りに気がついたのか、一人の画家が父に尋ねる。
「え、息子さんですか?」
「顔も性格も似てないがな。おらモタモタするんじゃねえ、早く作業に戻れ」
「マクベインさんを放っておけないですよ」
「じゃあ教会のやつら呼んで来い。手当てはそいつらに任せるさ。お前ら、早くしねえと漆喰が乾いちまうだろ」
フレスコ画は生乾きの漆喰に絵を描く。漆喰が乾く前に描ききらないといけないから、 一度作業を始めてしまうとあとはスピード勝負だ。
父は筆が早い。 彼の作業スピードを見越して漆喰を塗ってしまったのだとしたら、彼の穴埋めをこなすのは至難の業じゃないだろうか。
予想は当たっているらしい。画家たちは深刻そうな顔を見合わせ、ひそひそと話をする。
父は彼らに一瞥をくれたあと、信じられない言葉を言った。
「俺の分は息子に描かせる」
何を言ってるんだ、こいつは。 あれだけ僕の絵をけなしておいて、いまさら”代わりに描け”? 冗談じゃない。そこまで僕を笑いものにしたいのか。
画家も同じことを思ったらしい。少なくとも、これは得体の知れないやつと一緒に作業できる仕事ではない。
「けど、マクベインさん、彼は……」
部下の言葉を尻目に、父は僕のカンバスをまだ強引にひったくった。 そして、布を取り去る。
「これが描けるんなら、任せちまってもいいだろ」
未完成のエミリアさんの絵を周りの画家全員に晒された。
なんてことだ。父は僕の心を折るどころか、粉々に破壊したいのか?
周りの目を見る。それは、僕の予想とは逆だった。 彼らは目を見開いて、絵をじっくりと眺める。顔を近づけるもの、覗き込む者、笑顔で感想を言う者。
どういうことだ。まさか、父は僕の絵を認めたうえで見せたのか?
僕はよほど不思議そうな表情を浮かべていたらしい。父はくすりと僕の顔を見るなり笑って、それから周りの画家に言った。
「異論はねえよな。分かったら作業開始だ!」
画家たちは立ち上がり、座り込んだままの僕の腕を引く。 天井への足場へと向かう途中、父の顔を振り返ると……。
彼は、笑っていた。
Ⅱ-3
エミリアさんに絵の仕事を依頼されてから、一月がたった。
フレスコ画の事件のあと、僕は何事も無かったかのようにエミリアさんと目を合わせることが出来た。 もう、あの金色の瞳を見ても怯える事はない。
前と変わらず、穏やかな気持ちで彼女と向き合うことが出来た。
エミリアさんにフレスコ画のことを話したら、彼女は驚いて、そして祝福の言葉をかけてくれた。
”聖堂の絵にあなたの色が加わってるなんて。とっても素敵”と。
そして今日、僕はまた件の聖堂へ足を運ぶ。 絵を描くためではない。絵を、納品するためだ。
ピエトロ司祭と約束の時間に会い、エミリアさんの肖像画を見せる。 完成した彼女の絵は、やわらかい日差しのような微笑を浮かべる。 司祭は絵をじっくりと眺めたあと、安堵のため息をついた。
「本当に良かった。一時期はどうなることかと思いましたが」
「エミリアさんが……彼女が、工房まで毎日足を運んでくれたおかげです。彼女がいなければ、 僕はこれを完成させることは出来なかった」
エミリアさんが工房まで足を運び、元気付けてくれなければ。 僕はもう一度聖堂まで足を運ぶことはなかっただろう。 画家としての義務感もあった。しかし今思うと、エミリアさんの絵だからこそなんとしても完成させたかったのだ。 司祭は言う。
「何故、私があなたに依頼をしたのかエミリア様からお聞きになりましたかな?」
「いいえ」
「彼女には貴族のご友人がいましてね。そのご友人の肖像画をいたく気に入っていたのですよ」
まさか。
「その肖像画の持つ雰囲気や、温かみが好きなのだと。それを描いたのが、あなただったのですよ」
じゃあ、肖像画の依頼に僕を選んだのはエミリアさんだったのか。
僕は少し照れくさくなって、微笑した。
「彼女に、なんとお礼を言ったらいいか」
「直接言えばいいじゃないですか。今は、問題のフレスコ画を眺めていらっしゃいますよ」
「えっ」
彼女は席を外しているんじゃなかったのか。 驚いて顔を上げた僕に、司祭は笑う。
「納品作業に時間をかけるのもなんですし、エミリア様にご挨拶されてはいかがですか?」
実際、エミリアさんに言いたい事はいっぱいある。いても経ってもいられず、僕は司祭に一礼して席を立った。
「若いとは、実に良いものですなあ」
後ろでそんな声が聞こえた気がした。
*
エミリアさんは、フレスコ画の下で絵を見上げていた。
あの絵はもう完成している。 女神が扉を背に立ち、3つの世界に神託を下す様子が描かれている。 似たような題材の絵は過去に何枚も描かれているが、これほど大規模なものは初めてなのだと。
女神と良く似た後姿に、僕は呼びかける。
「エミリアさん」
はっ、と彼女は振り返る。 その金の瞳は、大きく見開かれて。
「マクベインさん? どうしてここに」
「……絵の納品に」
「そう、あの絵はとうとう完成したんですね。おめでとうございます」
「いえ。エミリアさんがいなければ完成はしませんでしたよ」
そういうと、彼女は首をかしげた。
「え、でも題材となる方がいらっしゃらないと、そもそも肖像画は描けないでしょう」
「そういう意味じゃあありませんよ」
声を上げて笑った。彼女は鈍感なのか、たまにこういう発言をする。 そういうところがあどけなくて、かわいらしいのだが。
ひとしきり笑うと、僕は改めて彼女に向き直った。
「とにかく、ありがとう。あなたが支えてくれなかったら、僕はもしかしたら二度と絵筆を握れなかったかもしれない」
エミリアさんはキョトンとした顔をしていた。が、その顔はしだいに微笑みに変わった。
「私こそ。あなたみたいな素敵な人に出会えて、本当に良かった」
その表情を見て、僕はすこし動揺した。 色白の肌に、うっすらと上気したような赤が差している。 彼女は顔を赤らめながら微笑んでいた。 いつもの彼女の表情ではない。何かが明らかに違う。 彼女は僕とばっちりと目を合わせ、うっとりとしたような表情で微笑み続けるのだ。
なんだ、何だ。彼女はいったいどうしたんだ。
「お世辞が得意なんですから」
とりあえず視線を逃がしつつ、僕は言った。
「お世辞じゃありません。司祭から、絵の依頼の話は聞いたでしょう?」
聞いた。確かに聞いたが。
なんで彼女の顔は赤いままなんだ。 それより、何で僕はこんなに落ち着きがないんだ。
気がつくと、僕はまた目をそらしていた。
父の姿がフラッシュバックしたからではない。 どちらかというと、あの雨の日の感覚に近いが、それとはまた違う。
彼女の金の目を見つめられない。
自分の変化に動揺しながらも、僕はふと気がついた。昔感じたことのある、この感覚。そうか、これは――
そして僕は、理解した。彼女に対する感情の変化に、気がついてしまった。
ひと呼吸おいて、僕は彼女の名を呼ぶ。
「エミリアさん」
「はい」
彼女は少し緊張した顔つきで、僕を見つめる。僕も、高鳴る鼓動を抑えながら彼女の眼を見つめた。 嫌な汗をかいている。彼女と始めて会った日と似ていて、だけど少し違う緊張感。
絵の仕事は終わった。もう、僕は彼女と会う理由はない。
だけど――
「エミリアさん、僕は――」
Ⅱ-4
僕は、一枚の絵を描いている。
大きなカンバスに、二人の人間。一人は金髪に金の瞳の女性、もう一人は黒髪に黒い瞳の男。 描き始めたのは一年前、彼女と出会ってひと月が経った日だ。そして完成時期は、未定。
「また描いてるの?あなた」
後ろでエミリアの声がする。
彼女は僕のことを”あなた”と呼ぶようになった。
僕はもうマクベインではない。
姓は、セフィリア。
僕は腰掛けたまま、エミリアの方を振り返る。 カツン、と首から提げた十字架のネックレスが絵にあたった。 エミリアは苦笑する。
「もう、だから服の中にしまって描いたらって言ってるのに」
「君だって、ネックレスしたまま料理するじゃないか。そのうちネックレスもろとも焦がしちゃうよ」
笑いながら冗談を返す。 彼女の料理はちっとも上手くならない。相変わらず消し炭の練成だけは上手だ。 だから、あながち冗談でもないのだが。
「今に上手くなってみせるわ。いつか出来る子どもに、お母さんの手料理食べさせてあげるの」
「楽しみにしてるよ」
エミリアと、僕のネックレスが揺れる。
いつかは、僕たちの間にも子どもができる。 それまで、この絵は完成する事は、ない。
”家族”と名づけた肖像画に、僕はこれからも、筆を入れていく。
End