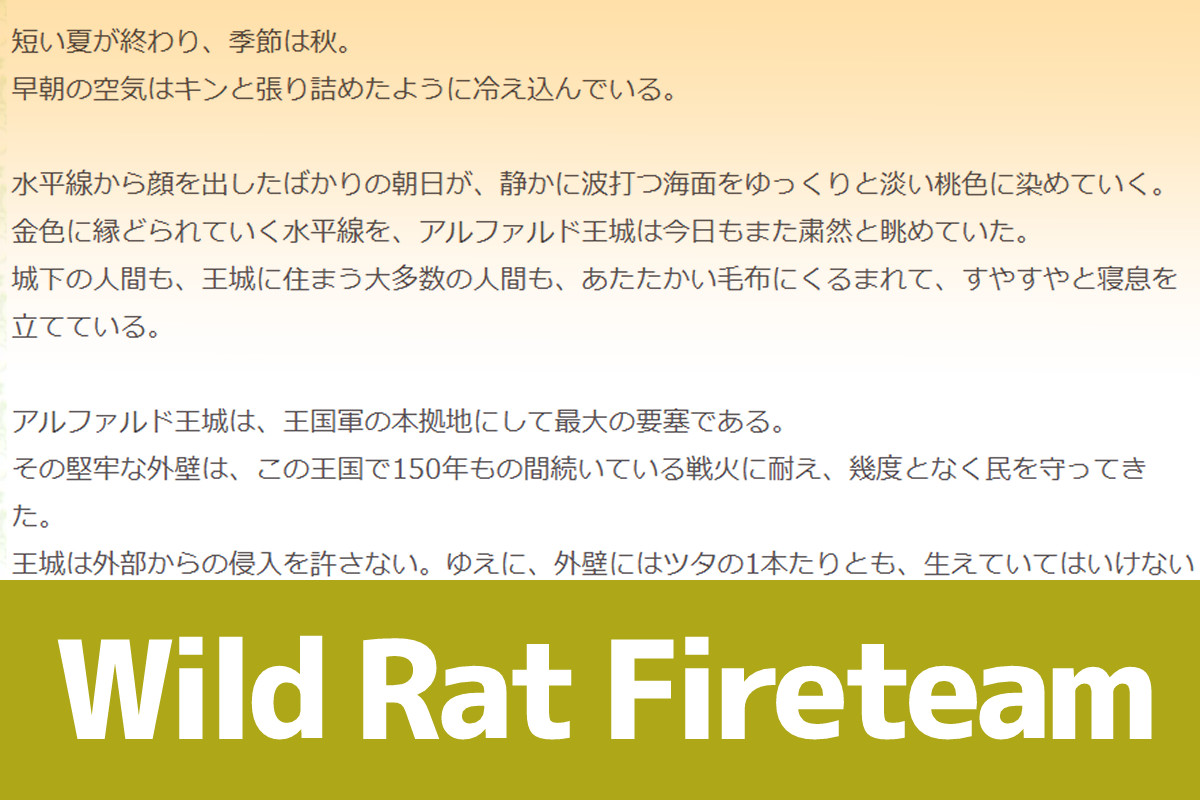第7話
時間は3年前にさかのぼる。
1733年、初秋。
テセラが城を逃亡し、エスト少年とディーナ兵士の説得によって城へ戻ってから、数日後のある日。
その日は、とてもよく晴れていた。
この日もアルファルド城内の人間は忙しく動いていた。
数日前に受けた、敵軍の急襲による損壊箇所を復旧するためだ。
急襲はごく小規模のものだったので、損壊箇所もごくわずかなものであった。
負傷した兵士の手当て、魔力を消費した魔導師団の魔力回復、使用した矢の手配や武器の補修……
その他もろもろの手配に、城内の人間は誰もが追われていた。
使用した武器や、消耗した防具。軽傷を負った兵士。
失ったものはあるが、それらは、「時間をかければ元通りになる」ものばかりだった。
だから、これは大丈夫。いつものこと。普段通りにやっていれば、平気なはずだ。
城内の人間は、皆がそう思っていた。それは、テセラとて例外では無かった。
数日前、テセラは城を逃げ出していた。
長く伸ばしていた髪を自分で切り、侍女の服までちゃっかりと手配した。
彼女の中では、かなり大規模で、計画的な犯行だった。
だが、それは失敗に終わった。
逃亡先の城下町で出会った、エストと名乗る貧民街の少年。そして、自分の身を案じて街まで追いかけに来たディーナ少将。
この2人の説得に、テセラは応じたのだ。
もう、私は逃げない。
その決意を胸にし、テセラは王城に再び戻った。
「姫」としての役割を受け入れたテセラは、自ら率先して自分の仕事を見つけに行った。
時には戦闘で負傷した者に声をかけに行き、時には書類整理に追われていた大臣を手伝ったり。
城の誰もが忙しく駆け回っているのに、自分だけ手をこまねいている場合では無かった。
城内の皆の顔は、明るかった。
「数日経てば、また元通りですよ」
誰もが皆、そう言った。
そしてテセラも、その言葉を信じて疑わなかったのだ。
***
軍事棟 中庭。
1階の通路を通り、中庭から中央棟へ通じる扉を開けようとした時だった。
ドアノブにかけた手に、ぽつりと一滴の雨粒が落ちた。
……さっきまで晴れていたのに。
そう思って、テセラは訝しげに空を見上げる。
と、中庭の壁で丸く切り取られた曇天を、ゆっくりと巨大な何かが横切った。
その「何か」は、そのまま城の北の方へ飛び去って行く。
テセラは思わず硬直した。あの巨大な翼を、見間違うはずもない。
それは……間違いなく、敵軍のドラゴンだった。
***
奇襲の警報が発令されたのは、そのわずか10分後。
突然で、そして予想外の警報に城内が一斉に慌てふためいた。
けたたましく響く鐘の音。
足早に走り去る軍靴の音。
幾重にも重なる、ドラゴンの咆哮。
装備を整えることもままならず、ルグレス軍に蹂躙されていく仲間たちの断末魔。
中央棟に避難したテセラを襲ったのは、それらの「音」だった。
近衛たちに取り囲まれ、テセラは部屋で座って待機を命じられた。
それが、彼女には耐えられなかった。
ねえ、私はここにいていいの?
そう聞きたくても、周りの近衛は互いに絶えず通信機で連絡を取っており、取りつく島もなさそうな様子だった。
背を向けた窓から響いてくる、悲鳴、咆哮、炎の音。
……その音は、少しずつ幼い王女の精神を削り取っていく。
ダメだ。
このままではいけない。
私は、自分で出来ることをしなくちゃ……!
通信機で連絡を取る近衛を遮ってでも、テセラはこの状況下を脱出したかった。
声をかけようと椅子から立ち上がったと同時に、部屋のドアが開いた。
部屋を訪ねてきたのは、魔導師団のシエナ元帥だった。
薄茶色の自慢の長髪と、上質な布でできた真っ白な服は、すっかり乱れている。
普段は何事にもどうじない、あのシエナ元帥が。
動揺している。
事態の重さを、テセラは改めて感じ取る。
シエナは上がった息を整えると、言った。
「……テセラ姫を、お借りできるかしら」
傍の近衛が通信を切り、応答する。
「元帥、何用ですか」
「オフィーリアから召集がかかったわ。”結界”を使う」
「結界?」
何のことやら、と近衛は首をかしげる。
あなたは何も聞いていないのね、とシエナはぽつりとつぶやき、テセラの方へ向き直った。
「テセラ姫。”結界”の話は聞いていますね。あれは試作段階ですが、完成を待つ前につかわなければいけないみたいなの」
テセラは、シエナの言葉にゆっくりと頷いた。
”結界”。それは、緊急事態の際にアルファルド王城と城下町を守るための防御魔法。
シエナ達が率いる魔導師団が実験的に開発している……という話を、以前テセラは聞いたことがあった。
テセラの頷きに、シエナは少しだけ表情を緩める。
「テセラ様。あなたが成すべきこと……いえ、あなたでなければできないこと。わかるわね」
「……ええ」
テセラはそう答え、シエナの元へと歩み寄る。
シエナは頷きながらテセラの手を取った。
***
結界の発動陣は、魔導師団第3実験室にある。
実験室の北側には、大きな窓が据えられており、そこからは城下町を一望できる。
窓から差し込む淡い日の光。それは分厚い曇天に覆われ、部屋を薄暗く照らすだけだった。
発動陣の中央には、金の細工で縁どられた透明の球体が置かれていた。
一見すると水晶玉のように見えるそれは、鈍い陽光を反射し部屋に鎮座している。
この球体が、発動陣の要となる。
術者の魔力を最大限に引き出すのが、この球体の役割だ。
引き出された魔力は、発動陣に刻まれた呪文により王城を守る結界を生成する。
テセラは重い足取りを進めると、発動陣の中央へ行く。そして、球体の手前で立ち止まった。
手をゆっくりと球体の上に差しのべる。
「シエナ。……準備できたわ」
シエナ元帥はゆっくりと頷く。発動陣の一歩外側に立っている彼女は、そのまま目を閉じると詠唱を始めた。
発動陣が、淡く白色に光り出す。
徐々に強さを増すその光に、テセラもまた瞳を閉じた。
球体は薄青い光に包まれ、やがては実験室全体をまばゆく照らし始める。

そして、一閃の後。
王城が、結界に包まれた。
***
結界は、テセラの魔力から作られている。
彼女の属性である「氷」から作られる結界は、王城と城下町の上空を覆い、敵軍の侵攻と飛竜の炎を防ぐ。
ゆえに、これ以上敵軍は入ってこられない。結界さえ張れてしまえば、あとは結界内に元々いる敵を掃討するのみ。
テセラとシエナはそう、思っていた。
***
結界の発動から十数分が経過した。
球体の中央で、テセラは発動時の姿勢を保ったままじっと耐えていた。
結界の生成には、術者の膨大な魔力が必要となる。
発動陣を起動させるだけのシエナとは違い、テセラの魔力は時間経過と共にどんどん消費されていく。
自身の魔力が少なくなるにつれ、彼女の身体は虚脱感とめまいに襲われていった。
……だが、テセラは最後まで耐えることにした。
ここで自分が倒れては、城を守れない。
発動陣の外側で、シエナはじっとテセラを見守る。
その時、シエナの持つ通信機から声がした。
「シエナ! 今どこにいるの?」
甲高い少女の声。オフィーリアだ。
彼女もまた、シエナと同じく魔導師団の元帥だ。
今はグレン元帥と共にキープへ向かっている筈、そうシエナは記憶していた。
シエナは通信機に向かって返答する。
「第3実験室よ。結界を発動させているわ」
「やっぱり……!」
同僚の声は、思った以上に焦燥している。
「シエナ。良く聞いて。今グレンたちと結界を確認したのだけれど……足りないの」
足りない?
何が?
「どういうこと?」
「範囲が、足りないのよ。結界の範囲が小さすぎて、王城と城下町の外周に近い部分が保護されていない!」
「えっ……!?」
シエナも驚嘆の声を漏らす。
足りない?
結界は、王城と城下町全域を保護できるような設定のはずだ。
それなのに、どうして範囲が小さすぎるのか?
混乱しかかる思考を巡らすシエナの向こうで、オフィーリアは続けた。
「テセラ様に、結界の範囲を調整するように言って。王城の南部はもう少し保護を。逆に、北側はすこし範囲に余裕があるわ。
できそう?」
「……でき、ると思うわ……けれど」
シエナが続けようとしたとき、声を潜めたオフィーリアの言葉が返ってくる。
「……魔力が足りてない。テセラ様がこの魔法を使うには、若すぎたのかも……」
シエナは、思わずテセラを横目で見た。
12歳の王女は、城を守らんとふらつく体で懸命に戦っている。
未成熟のテセラの身体には、この魔法は時期尚早だったのか……?
シエナは言葉を失う。
そんな彼女の前で、テセラはゆっくりと振り返った。
すでに表情からは余裕が消え去り、額には冷や汗が流れている。
「シエナ……いいの、全部、聞こえてた」
「テセラ、さま」
「オフィーリア。言われたとおりに調整、して、みたつもり……どう?」
シエナが沈黙している間に、テセラは結界の範囲を調整していたようだ。
通信機の向こう側で衣擦れと足音がしたのち、返答がきた。
「……ダメです。これでも足りない……!
もう範囲はギリギリなのに、城下町がまださらされてる……!」
シエナは、通信機を固く握りしめて話しかける。
「オフィーリア、誰か人を呼べない? テセラ様の代わりに結界を発動できる人がいれば」
「駄目よ……。誰かに代わってもらうにしても、一度発動を解かなきゃいけない。その隙を狙って、敵軍が一気に攻め込んでくる。
一度発動した結界は、最後までその人にやってもらわないと意味が無いわ」
「だけど」
「シエナ、現実を見なさい!」
オフィーリアの怒声が、シエナを一喝した。
シエナは、完全に沈黙してしまった。
もう、自分に出来ることは無い。
「テセラ様。……申し上げにくいのですが……。結界で保護される地域に、優先度をつけるしかありません」
「ゆう、せんど……?」
「人口密度の低い地域から、結界の保護を解除してください。そうすれば、多くの人命は守られます。発動時間も長く保てるはず」
「えっ……?」
保護を解除する。
それは、解除された地域の人達を見殺しにするのと同じだ。
優先度?
人の命に優劣をつけろというのか?
「……だめ、オフィーリア……。そんなの、できるわけない……!」
「ですが、テセラさま」
「私に、人の優先度なんてつける資格ない!」
「……じゃあ、このままあなたの魔力が尽きて、王城も城下町も全滅する道を選ぶんですか?」
「……。」
「あなたの魔力に関して、目測を誤った。その結果、結界を不十分な状態で発動させてしまった。それは、私達魔導師団の非です。
……なにも、責任をあなた一人で負えとは言ってない。私達も、結界の保護を解除した地域の損失に関しては責任を負います。
……だから、お願いです。少しでも多くの人が助かる道を、考えて」
テセラは愕然とし、膝をついた。
少しでも多くの人を?
そんなの、綺麗ごとじゃないか。
……けれど、自分の力では、その綺麗ごとにすがるしか、道は無い。
……父を、義母を、臣下を、近衛たちを、
見殺しにするなんて、できない。
テセラは、絞り出すような声でオフィーリアに問う。
「……オフィーリア……。人口密度が低い場所は、何処?」
短い沈黙の後、オフィーリアの声が返ってきた。
「……南東部の農耕地と、北西部の貧民街です」
貧民街。
その単語がテセラの耳に入った瞬間、彼女の脳裏にはあの少年の姿が浮かんだ。
貧民街の保護を解除する。それは、彼を見殺しにするのと同義だ。
彼女は思考し、逡巡し……そして、諦めを付けた。
「……その2か所を、解除すればいいのね……」
***
範囲が縮小された結界は、その後1時間にわたってアルファルド王城と城下町の一部を保護し続けた。
魔力を使い果たしたテセラは数日間昏倒し、魔導師団の処置を受けて回復した。
魔力が戻ったテセラが目にした光景は、
農耕地と貧民街が黒い焦土と化した城下町の風景だった。
***
結界の発動と、敵軍急襲の悲劇の日。あの日から、3年が経った。
結界の保護区域から外れ、敵軍の猛攻を直撃した貧民街。その生き残りの少年は、今、王国軍の制服を着て王女の隣に立っている。
エストは、テセラが涙ながらに話す間、ずっと黙って話を聞いていた。
「黙る」というより、「言葉を失って」の方が近いかもしれない。
3年前の悲劇についてテセラが話し終えてもなお、エストは何も言いだせずにいた。
絶句している彼の隣で、王女は続けた。
「私はあの日、スラムの人たちを見殺しにした。エストも、あの日私が殺してしまった……そう思っていた。
あなたの家を、家族を……私は奪ってしまったも同然なの……。
それなのに、私があなたの隣で笑っている資格なんて、あっていいはずがない」
「テセラ、だけど」
「ごめんなさい」
そういうと、テセラはバルコニーから背を向ける。
「さよなら」
そう言い残して、彼女は立ち去って行ってしまった。
第8話
翌朝、朝の訓練を終えたエスト達3人はいつものように食堂の「指定席」に腰を下ろしていた。
普段と違うのは、エレブランド曹長が会議のため席を外していること。
そしてもう一つ。
エストの食指が全く動いていないことであった。
ソフィーとサムエルは、目だけでお互いを見やる。
その眼差しは、2人とも事情を知らないと語っていた。
いつもなら、我先にと食事を口に運ぶエスト。
ソフィーとエレブランドが、彼の底なしの胃袋に唖然とした回数は計り知れない。
そのエストが。今日は全く食事をとろうとしない。
嫌な沈黙が、3人の間に流れた。
その空気に最初に耐えかねたのは、サムエルだった。
「……ねえエスト、どうしたの? どこか具合でも悪いの?」
友人のその問いかけに、エストは伏せていた視線をわずかに上げた。
「え? あ、ああ。食欲ないんだ」
サムエルとソフィーは、思わず耳を疑った。
食欲がない。
あのエストが。
彼の発言が衝撃的過ぎて、2人の脳内にはエストのセリフが何度もこだまする。
少しの間の後、ソフィーが椅子を蹴り飛ばさんばかりの勢いで立ち上がった。
「ウソでしょ!? アンタが、食欲無い!?
どうしたの、熱は!? まさか敵兵に」
「お、落ち着いてソフィー!」
混乱したソフィーを、サムエルが必死で止める。
ソフィーのことだから、このまま混乱を許せば逆にエストを殴り飛ばしかねない。
サムエルも椅子から立ち上がり、ソフィーをなだめながらゆっくりと座らせた。
「食欲がないなんて、珍しいね。どうかしたの?」
そう聞くと、エストの視線がわずかに泳ぐ。
どうやら軽い気持ちで話せるような事情では無いようだ。
サムエルは彼の表情を察すると、ソフィーに続いて自分もゆっくりと腰かけた。
「……今日はエレブランド曹長もいないよ。僕もソフィーも、話、じっくり聞くから」
優しく微笑んで、エストを諭す。
エストは、3年間一緒にいた友人なのだ。
そして、自分と共に王国軍の道を志した同士でもある。
今更、どんなことが彼の口から飛び出たって驚くもんか。
エストはサムエルとソフィーの表情を見比べると、昨日のテセラとのやり取りを、すべて話した。
***
「で、あんたはそれでどうしたいのよ?」
エストの話が終わると、開口一番にソフィーがそう言った。
エストの話す内容の重さについていけてないサムエルが、えっと言いたげな表情でソフィーを見る。
「どうって…」
エストは押し黙った。
テセラにさよならと言われたあと、自分もどうすることも出来ず、そのまま彼女の部屋から帰ってきてしまった。
あれで本当に良かったのか、と後悔の念は、無いわけでは無かった。
だが、どうすることもできなかったのだ。
エストは続ける。
「どんな顔をしてあいつに会えばいいんだよ……」
「じゃあ、このまま会わないつもり?」
エストは肯定も否定もしない。
「もともと、叶わない恋だって……わかってたんだ」
向こうは王女、こちらはなりたてホヤホヤの問題下級兵。
身分違いの恋は、いつかテセラを苦しめる。
……このままで十分だったのだ。
王国軍として、テセラを守れる立場に就く。
それが叶ったのだから、もう十分なのだ。
「でも、せっかく会えたのに…!」
やっとの思いでサムエルが言葉を紡ぐ。
だが、エストはその言葉を一蹴するかのように言った。
「2人が協力してくれたのは感謝してる。けど、向こうが会う気がない上に、身分が違うのは……しょうがないだろ」
そう言い放つと、エストはほとんど手つかずの自分の食事を持って立ち上がった。
「先に行ってる」
制止しようとしたソフィー達から背を向け、エストはそのまま食堂をでていってしまった。
「…何よあいつ、ヘコんじゃって…」
呟くソフィーの横で、サムエルが机に突っ伏した。
周囲からどんよりとしたオーラが見える様な気がして、ソフィーは思わず一瞬身を引く。
「うわっ、 こっちも!?
……あのねえ、あんたまで気に病むことはないのよ?」
「分かってるけど……」
そういうと、サムエルは顔をほんの少しだけ上げる。
「3年間、ずっと再会したがってたのにこんな結果になるなんてないよ」
”3年間 ずっと”。その語句にひっかかりを覚えたソフィーは、話題をそちらに変えることにした。
「そういえば、どうしてあんたはあいつのことそんなに詳しいの? 幼馴染み?」
ああそっか、と軽く言って、サムエルは顔を完全に上げた。元の姿勢だ。
「えっと、貧民街襲撃のことまでは話したんだっけ。その時、エストの家族は皆死んじゃったんだ……。
それで、貧民街をさまよってるエストを僕が見つけたんだ」
ここまで聞いて、ソフィーは察した。
「アンタが拾ったの?」
はは、と苦笑いし、サムエルは言う。
「そんな捨て猫みたいなこといわないでよ。……まあ、間違いじゃないのかもしれないね。
ローレンスの姓は捨てたくなかったみたいで、苗字は変えなかったんだ」
「なるほど。それで、3年間あいつはアンタのところで育てられた、と」
サムエルは小さく頷く。
「僕の家は昔から騎士の家系でね? 小さい頃から、僕も姉さんもこの道を選んでた。
エストも、家族のこととか、テセラ様のこととか……色々思うところがあったんじゃないかな。『オレも兵士になる!』って言ってきたの、そんなに日数はかかってなかったと思う」
ここまで言って、サムエルは再び顔をうつむけた。
「だから、放っておけないんだ。
でも、エストって強いし行動力があるから、どんどん僕の先を行っちゃうんだ。
僕ができることってすごく少なくて……」
うつむく角度が、だんだん深くなる。
「ねえ、僕はどうすればいいのかな……」
また、どんよりとしたオーラが見え始めてきた。
ソフィーは軽くため息をつくと、サムエルの肩をポンと叩いた。
「まずは、そのネガティブ思考から改善することね」
「え?」
「人を元気にしたいなら、まずアンタが元気にならなくちゃ。
そしたら、2人で作戦会議しましょ?」
WRF8
ソフィーの優しく、そして頼もしい表情に、サムエルの顔もほころんだ。
「……うん!」
***
エストの食欲はサムエルとソフィーの尽力によって回復を見せたが、それでも彼の足は中央棟へ出向くことは無かった。
そして、月日は流れていく。
赤々と輝いていた木の葉が、日に日に彩度を失っていく。
冷たく凍えるような風に吹かれて、一枚、また一枚と落ちていく。
長く厳しい、忍耐の季節がすぐそこまで来ていた。