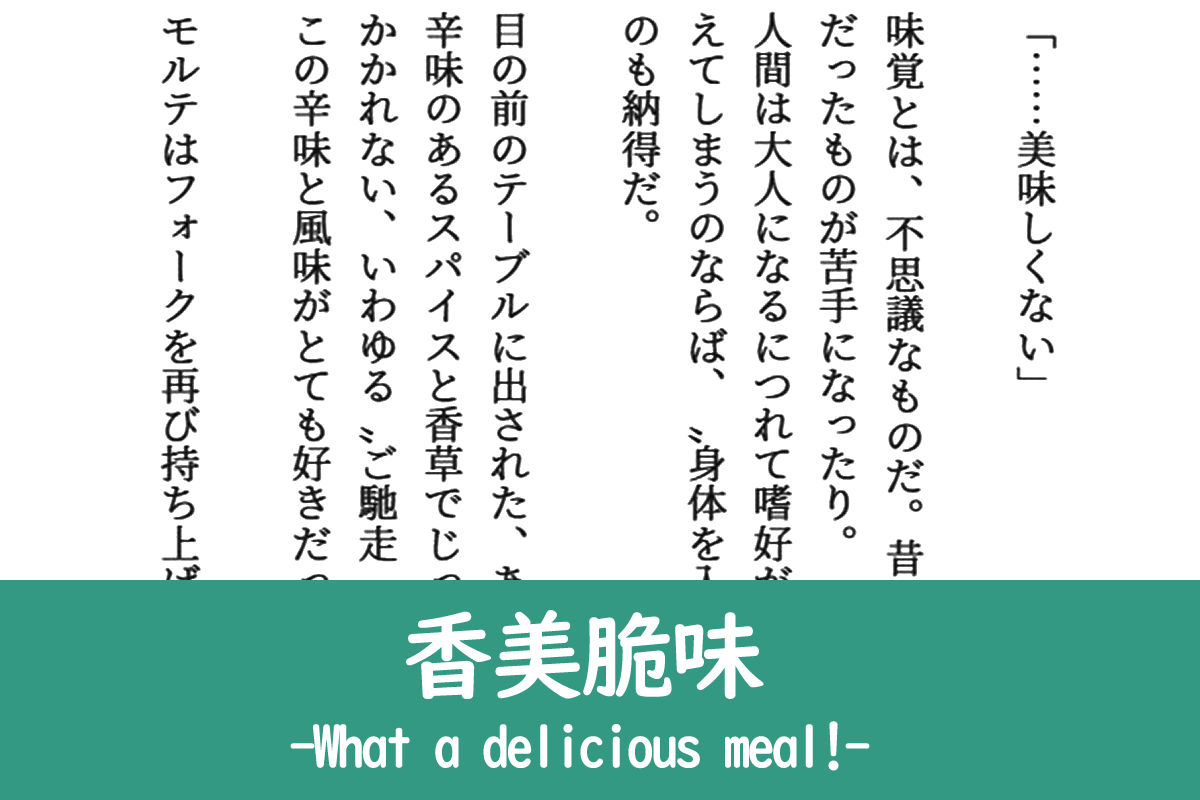本編4章冒頭のネタバレが含まれます。
「……美味しくない」
味覚とは、不思議なものだ。昔は苦手だった食べ物が好物になったり、逆に好物だったものが苦手になったり。
人間は大人になるにつれて嗜好が変化するという。肉体の成長が食の好き嫌いを変えてしまうのならば、”身体を入れ替えた”場合は味覚ががらりと変化してしまうのも納得だ。
目の前のテーブルに出された、あつあつの肉料理。一口大に切られた鳥の胸肉を、辛味のあるスパイスと香草でじっくりと焼き上げた――この地方ではあまりお目にかかれない、いわゆる”ご馳走”。
この辛味と風味がとても好きだった。前の身体では。
モルテはフォークを再び持ち上げ、もう一かけらを口に運ぶ。
やはり、おいしくない。この香草の風味が好きだったのに。舌が本能的に忌避するかのように、辛味と風味を拒否している。
それでも残すのは良くない。義務的に皿を空にすると、隣のテーブルに聞えないように小さくため息をついた。
身体を入れ替えるのは、これが初めてではない。数十年間、新しい依り代を見つけては何度もやってきたことだ。体格、体質、病気――肉体依存の微細な仕様変更に悩まされてきたが、今回の変化は少なからずショックだった。
――まあ、仕方ないか。
今回は老衰寸前の老いぼれから、ガリガリに痩せこけたガキに乗り換えたのだ。肉体のすべてが、これまでとは違う。受け入れなくては。
だが、これではまた”好きな食べ物”を見つけ直さなくてはいけない。食べることは嫌いではないが、トライ・アンド・エラーを繰り返すよりも一発で最適解を見出したい性分なのだ。
『カナール』と呼ばれていた子供。いったい此奴は、何が好きなのだろう。あまり食に興味を持っているような印象は受けなかったが。
テーブルの隅に立てかけられている、メニュー表に視線を移す。まだ胃の容量には余裕がある。
子供の舌でも受け入れられそうな料理は――料理の羅列を下っていき、ある名前が目に留まった。
***
十数分後。
モルテが座る席に置かれたのは、小さい皿にちょこんと乗った、卵料理だ。
温められた牛乳に砂糖と卵を混ぜ、蒸し焼きにして作られる――カスタード・プディングと呼ばれる甘いデザート。
料理を持ってきた店員が、去り際に微かに微笑んでいた。端から見れば、実に子供らしい注文に見えたのだろう。その態度が癪に障ったが、今回ばかりは許してやることにした。食は生きていくうえで必要不可欠だ。これは食の質を向上させるための実験なのだから。
スプーンを手に持ち、プディングの側面を軽くつつく。柔らかく黄色い生地に亀裂が入り、銀色の曲面に一口分のプディングが乗る。モルテは徐に口に運ぶ。舌の上に乗る卵の風味、まろやかな舌触り、優しい甘み。
「……美味しい」
予想は的中していた。やはりこの身体は、素直に子供らしい甘いものを好むようだ。
モルテは不服だった。もう少しこの舌が、大人びた嗜好を持っていればよかったのに。
注文の度におこさまランチを頼むわけにもいかない。それは自分の、偉大なる魔導書としての矜持が大きく損なわれる。
この身体の持ち主に、嫌みの一つでも言い放ってやろうか。せっかく魂が残っているのだ、クレームの一つや二つ、言っても罰は当たらないだろう。
《カナール。カナール、聞こえてる?》
意識の深層に問いかける。カナールは、相変わらず貧相な顔つきで膝を抱えて――いるかと思っていた。しかし今回は違っていた。赤い瞳を輝かせ、何故か頬は上気している。
《なに、気持ち悪い。風邪でも引いたの?》
モルテは怪訝な表情を隠さなかった。
カナールは何も言わずに、視線をモルテから逸らした。しかし、平時の無気力な瞳ではない。明らかに、何かが起きたのだ。それも、ポジティブな何かが。
《……まさか、カナール……》
表に出てこないカナールが、自分の知らないところでイベントに遭遇するはずがない。これは傍観者だ。ということは、今しがたモルテも体験した何かが、カナールにとってプラスの作用をもたらした。そうとしか考えられない。
《プディング、食べたの初めて?》
モルテの問いに、カナールは恥ずかし気に頷く。
二、三度、こくこくと頷くカナールの顏は、口こそ閉じていたが驚きと歓喜の眼差しに溢れていた。
――やっぱりこのプディング、残してやろうか。
モルテの意地悪な思惑が見えたのか、カナールは首を横に振りながらモルテの後ろ髪を引くのだった。
極めて贅沢な食事のこと。「香美」は香辛料のきいた、よい香りのする料理。「脆味」は柔らかい菓子。